子の引渡しを成功させて親権を獲得する方法と知っておくべき5つの事

「配偶者が突然子供を連れて家を出ていった」
「連れ去られた子供を取り戻したい」
このとき、無理に子供を連れ戻そうとしてはいけません。
法的な手段を経ることなく、自らの手で子供を連れ戻そうとした場合、状況によっては未成年者略取罪などの罪に問われる可能性があります。
また、親の身勝手な理由で子供の環境がコロコロ変わることは子供の福祉を損なう恐れがあります。
このような場合は、法的な手続きである子の引き渡し請求を行うことが大切です。
この記事を最後まで読むことで以下のことがわかります。
・離婚前・離婚後別の子の引渡しの請求方法
・離婚前の監護者指定・子の引渡しの重要性
・子の引渡しで考慮される要素
・相手が子の引渡し命令に従わない場合の対処法
・子の引渡しで知るべきこと
- 目次
子の引渡しの請求方法
子の引渡しについて父母間の話し合いで解決しない場合は以下の方法で対応します。< /p>
- 子の引渡し調停
- 子の引渡し審判
どちらも裁判所の手続きですが、調停は当事者同士の話し合いである一方、審判は双方の言い分を聞いた裁判所が判断をくだす手続きです。
通常、家事事件は当事者同士の話し合いによる解決を目指します。そのため、まずは調停を申し立てるというのが原則です。
しかし、子の引渡しに関しては、話し合いで解決できる可能性が非常に低いといえます。
また、緊急性が高いケースも多いため、最初から審判を申し立てるケースがほとんどです。
なお、子の引渡し審判は、状況に応じて下記の手続きを同時に申し立てる必要があります。
- 離婚前:監護者指定調停・審判
- 離婚後:親権者変更調停・審判
下記で離婚前と離婚後、それぞれのケースにおける子の引渡し手続きを解説します。
離婚前
離婚前の子の引渡し、監護者指定の審判の流れは以下のとおりです。
- 子の引渡し、監護者指定の審判を同時に申し立てる
- 第一回の審判期日
- 調査官が調査を行い、調査報告書を作成する
- 第二回審判期日
- 審理終結
- 審判
前述のとおり、離婚前は監護者指定審判を同時に申し立てます。
離婚前は父母が共同で子供の親権者となっています。
そのため、子供と同居して養育監護を行う監護権を夫婦のどちらか一方に指定したうえで、裁判所から子の引渡し命令が出されることになります。
審判の期日は通常二回程度ですが、状況によっては三回、四回と期日を重ねることもあります。
離婚後
離婚後の場合は子の引渡しと親権者変更の申立てを同時に行います。
離婚後に親権者でも監護者でもない親は子供を養育監護する権利がありません。
そのため、まずは親権者を自分に変更したうえで子の引渡しを行う必要があるのです。
なお、親権者変更は子供の環境を大きく変更することになります。
親権者を変更する理由や子供の意思、現在の子供の養育状況などを総合的に鑑みて、慎重に判断されることになります。
審判前の保全処分
子の引渡し請求では緊急性を要するケースが多いです。そのため、審判前の保全処分も併せて申し立てるケースが一般的です。
審判前の保全処分とは、権利の対象を保全することを裁判所に求める手続きをいいます。
子の引渡し請求の審理には半年から一年半程度かかることもあります。
そのため、当事者同士が争っている間に子供の心身が危険に曝されてしまう恐れがあります。
このような場合、審判前の保全処分を併せて申立てることで、子供の置かれた環境が劣悪な状況であるような場合に保全処分が認容される可能性があります。
保全処分が認容され、保全の必要性が明らかに高いと認められるケースであれば、申立から1~2か月程度で保全処分の命令が下され、仮に子の引渡しを命じてもらうことができます。
離婚前の監護者指定・引渡しは親権獲得で重要になる

離婚前の子の引渡しと監護者指定の審判は離婚成立までの一時的なものです。
しかし、これらが認められると、その後の離婚裁判における親権争いで有利に働きます。
例えば、離婚裁判に進めば、離婚成立までに通常半年から数年程度時間がかかる可能性があります。
一方、離婚後の親権者指定においては、監護の継続性が重要視されます。
離婚成立までの間、監護者として子供を養育すれば、子供の長期的な養育実績を積みあげることになります。
これにより、離婚訴訟において親権者を獲得できる可能性が高くなります。
子の引渡しで考慮される5つの要素
子の引渡しを認めるかどうかについては子の福祉や利益の点から総合的に判断されることになります。具体的には下記の要素が郷慮されることになります。
- 子の連れ去り行為の違法性
- 引渡し後の養育環境
- 親の監護実績
- 子供の現状
- 子供の年齢、意思
それぞれについて下記で解説します。
子の連れ去り行為の違法性
子供を連れ去った行為に違法性が認められる場合は、その事実が子の引渡しを認める理由として考慮される可能性があります。
例えば、違法性があると判断されるケースとしては以下のようなものがあります。
- 子供が嫌がっているのに無理やり連れ去った
- (元)配偶者をだまして連れ去った
- 暴力的な方法で子供を連れ去った
- 面会交流の際に子供を同居する親の元に帰らせずに連れ去った など
引き渡し後の養育環境
引き渡し後の養育環境も考慮される要素です。
請求した側の子供を養育できる環境が整っておらず、連れ去った側の養育環境のほうが整っていれば、引渡しは認められにくくなります。
引渡した後の養育環境が整っているかどうかについては、以下のような要素が考慮されます。
- 親族など育児に協力してもらえる人がいるかどうか
- 親の健康状態に問題はないか
- 育児休暇取得や短時間勤務が取得できる職場である など
親の監護実績
父母が同居していたときの子供の監護実績も考慮されます。
子供を連れ去った側の親が同居中に子供の養育を主に担っていた場合、引渡しは認められにくいといえます。
反対に、同居中ほとんど養育に携わっていなかった側の親が子供を連れ去った場合は引渡しが認められやすいといえます。
子供の現状
連れ去られた後の子供の現状も考慮されます。
連れ去られた後の子供の養育環境が劣悪なものであったり、子供が適切に養育されていない場合は引渡しが認められやすくなります。
一方、連れ去られた後、子供が適切に養育されており、学校や幼稚園などにも通常どおり通い、安全かつ平穏に生活している場合は引渡しが認められにくくなります。
子供の年齢、意思
引渡し請求手続きでは、子供の年齢や発達状況に応じて子供の意思が尊重されます。
例えば、子供の年齢が15歳以上の場合は裁判所が子供の意見を必ず聴取することになっています。
基本的に子供の年齢が10歳以上であれば意志表示ができるとみなされ、子供の意思が尊重される傾向があります。
相手が子の引渡し命令に従わない場合

子の引渡し審判や審判前の保全処分などを申立て、裁判所から子の引渡し命令が出たにも関わらず、相手方が命令に従わないケースもあります。
このような場合の対処法について順を追って解説します。
任意で引渡しを行うよう促す
相手方が裁判所の命令に従わない場合は強制執行を申し立てることになります。
しかし、強制執行は申立て側や引き渡される子供の負担が大きい手続きです。
まずは相手方が任意で子供を引渡すよう促すことを検討しましょう。
相手方が引渡し命令に従わない理由として、「子供を引き渡さなくても問題ない」と思っている可能性があります。
そのため、法的に引き渡す義務があることを相手方に説明することで引渡しに応じる可能性があります。
もし、相手方に弁護士がついている場合は、弁護士に対して引渡しするように伝えると良いでしょう。
裁判所の命令に背き、子供の引渡しを拒み続ければ、結果的に強制執行で子供と引き離されることになります。
また、裁判所の命令に従わないことで、監護者としての適格がないとして、親権争いで不利になる可能性があります。
さらに、離婚後の面会交流も実施できなくなる恐れがあり、一生子供と会えなくなる可能性があります。
もちろん、弁護士は依頼者の利益のために行動します。
しかし、上記のリスクを考慮すれば、依頼者が子供を引き渡さないことが真に依頼者の利益になるかどうかを判断できます。
そのため、総合的かつ合理的に判断したうえで、相手方を説得してくれる可能性があります。
強制執行を行う
子の引渡しの強制執行は以下の2つの種類があります。
間接強制:間接強制金を課すことで、相手方に引渡しを促すもの
直接的な強制執行:間接強制を行っても子供を引き渡さない場合や引き渡す見込みがない場合に家庭裁判所の執行官が子供のいる場所に赴き、直接的に子供を連れ戻すもの
なお、子の引渡しの強制執行は間接強制前置が原則であり、直接的な強制執行を申し立てる前に間接強制を検討すべきとされています。
人身保護請求を行う
家事手続により子供の引渡しが認められたにも関わらず、相手方が子の引渡しをせず、強制執行もできない場合は人身保護請求の手続きを行います。
人身保護請求とは、人身保護法に基づき、人身の自由の回復を請求することをいいます。
人身保護請求が認められれば子供を取り戻せる可能性は高くなります。
ただし、人身保護請求が認められるためには以下の要素を満たすことが必要であり、必ず認められるとは限りません。
- 相手方が子供を拘束している
- その拘束の違法性が顕著である
- 他の方法では相当の期間内に救済の目的を達せられないことが明白である
特に離婚前の連れ去りの場合、②の拘束の違法性が顕著であることの認定は難しくなります。
また、人身保護請求を行う場合、法律上、必ず弁護士を代理人に立てなければならないとされています。
子の引渡しで知るべき5つのこと
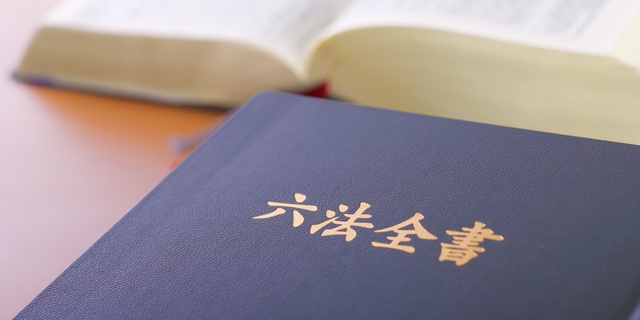
子の引渡し請求を行う前に下記の5つのことを知っておきましょう。
- 裁判所の判断基準を把握しておく
- 迅速かつ適切に申し立てを行う
- 審理期間
- 審判結果に不服がある場合の対処法
- 審判前の保全処分の不服申し立て
それぞれについて下記で解説します。
裁判所の判断基準を把握しておく
子の引渡しが認められるためには、裁判所の判断基準を把握することが重要です。
前述したとおり、子の引渡しでは以下の要素を考慮したうえで、子の福祉に適うかどうかという視点で判断を行います。
- 子の連れ去り行為の違法性
- 引渡し後の養育環境
- 親の監護実績
- 子供の現状
- 子供の年齢、意思
特に、連れ去りに違法性があるかどうかは非常に重要な要素です。連れ去りに違法性があると評価された場合、子の引渡しが認められやすい傾向があります。
もちろん、違法性だけで子の引渡しが判断されるわけではありません。
そのため、子の養育監護の協力者を得る、子育てしやすい就業条件に変更するなど、引渡し後の養育環境を整えることなども重要です。
迅速かつ適切に申し立てを行う
連れ去ったあとの相手方の養育監護の期間が長くなればなるほど、引渡し請求は不利になります。
そのため、引渡し請求の申立てはできるだけ迅速に行うことが大切です。
もちろん、申立は早ければ良いというものではありません。
引渡し請求が認められるためにも、裁判所に提出する書類は適切に記載し、主張を立証するための証拠などを集めておくことも重要です。
審理期間
子の監護者指定や引渡し審判の審理期間は半年から1年半程度が通常です。
そのため、連れ去られ後の子供の置かれた環境が劣悪なものである場合、前述のとおり、審判の申立てと同時に審判前の保全処分を申し立てておきましょう。
保全処分の要件が認められれば、申立から数ヶ月で保全処分の命令が出るのが一般的です。
審判結果に不服がある場合の対処法
審判結果に不服がある場合は即時抗告を申し立てることになります。
即時抗告とは裁判所の命令に対して行う不服申し立て手続きのひとつです。
即時抗告は請求側、請求された側を問わず申立てが可能です。
なお、即時抗告ができるのは審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内となっています。即時抗告がなされなければ、審判が確定します。
一方、即時抗告がなされた場合は高等裁判所で争うことになります。
審判前の保全処分の不服申し立て
審判前の保全処分の申立てが却下され、納得できない場合も即時抗告の申立てを検討しましょう。
一方、審判前の保全処分が認められた場合、相手方が即時抗告の申立てを行うケースもあります。
もっとも、すでに認められた審判前の保全処分は即時抗告によって直ちに効力が失われるわけではありません。
そのため、即時抗告がなされた場合であっても、子の引渡しを求めることができます。
まとめ
子の引渡しについて解説しました。
子の引渡しを請求する際は裁判所の判断基準を押さえたうえで、できるだけ早く申立てを行うことが重要です。
特に、離婚前の監護者指定・子の引渡し審判は離婚時の親権争いにおいても重要になります。
また、子の引渡しは離婚前と離婚後で同時に申し立てる手続きが異なります。
子の引渡しを行う際は裁判所の判断基準を押さえたうえで、適切に申立て・主張を行う必要があります。
有利に子の引渡し手続きを行うためにも専門家である弁護士のアドバイスを受け、適切に行うことをおすすめします。
都道府県から弁護士を検索する
離婚コラム検索
離婚の親権・養育費のよく読まれているコラム
-
 1位親権・養育費弁護士監修2020.03.30養育費を払わない方法|払えない・払いたくないなら知るべき7つのこと子供を持つ夫婦が離婚すると、親権を持たない親は親権者に対して養育費を支払う必要が...
1位親権・養育費弁護士監修2020.03.30養育費を払わない方法|払えない・払いたくないなら知るべき7つのこと子供を持つ夫婦が離婚すると、親権を持たない親は親権者に対して養育費を支払う必要が... -
 2位親権・養育費弁護士監修2019.02.28離婚後に扶養控除はどうなる?子供がいる場合の扶養手続き専業主婦やパートタイマーなどをしていて子供と夫の扶養に入っている人も多いでしょう...
2位親権・養育費弁護士監修2019.02.28離婚後に扶養控除はどうなる?子供がいる場合の扶養手続き専業主婦やパートタイマーなどをしていて子供と夫の扶養に入っている人も多いでしょう... -
 3位親権・養育費弁護士監修2019.07.29子連れ再婚|子供を連れて幸せな再婚をするために知るべき7つのこと1人で子供を育てていると、心細くなったり、誰かに支えてもらいたいと思ったりするこ...
3位親権・養育費弁護士監修2019.07.29子連れ再婚|子供を連れて幸せな再婚をするために知るべき7つのこと1人で子供を育てていると、心細くなったり、誰かに支えてもらいたいと思ったりするこ... -
 4位親権・養育費弁護士監修2019.01.15離婚後に子供を元配偶者と面会させたくない!拒否はできる?離婚して子供の親権を獲得した人が、元配偶者から「子供と会いたい」と言われたとき、...
4位親権・養育費弁護士監修2019.01.15離婚後に子供を元配偶者と面会させたくない!拒否はできる?離婚して子供の親権を獲得した人が、元配偶者から「子供と会いたい」と言われたとき、... -
 5位親権・養育費弁護士監修2019.01.10親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?子供を持つ夫婦が離婚する際に問題になるのは親権者指定です。親権獲得は母親のほうが...
5位親権・養育費弁護士監修2019.01.10親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?子供を持つ夫婦が離婚する際に問題になるのは親権者指定です。親権獲得は母親のほうが...
新着離婚コラム
-
 DV・モラハラ2026.01.21エネ夫の特徴と対策|妻を追い詰める正体と法的解決へのステップエネ夫(エネミー夫)という言葉を聞いたことはありますか?「味方であるはずの夫が、...
DV・モラハラ2026.01.21エネ夫の特徴と対策|妻を追い詰める正体と法的解決へのステップエネ夫(エネミー夫)という言葉を聞いたことはありますか?「味方であるはずの夫が、... -
 基礎知識2026.01.08婚前契約(プレナップ)の全て|メリット・デメリット・有効な書き方婚前契約と聞いてどのようなイメージを持ちますか?人によっては「離婚を意識している...
基礎知識2026.01.08婚前契約(プレナップ)の全て|メリット・デメリット・有効な書き方婚前契約と聞いてどのようなイメージを持ちますか?人によっては「離婚を意識している... -
 親権・養育費弁護士監修2025.12.08【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。しかし、「養育費だ...
親権・養育費弁護士監修2025.12.08【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。しかし、「養育費だ... -
 親権・養育費弁護士監修2025.11.17離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。面会交流...
親権・養育費弁護士監修2025.11.17離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。面会交流... -
 不貞行為弁護士監修2025.10.31不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド配偶者に不倫された!「不倫相手と別れさせたい」「配偶者は『もう別れた』と言ってい...
不貞行為弁護士監修2025.10.31不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド配偶者に不倫された!「不倫相手と別れさせたい」「配偶者は『もう別れた』と言ってい...
離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!
離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!
離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。
離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!
離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。












