離婚後に子供を元配偶者と面会させたくない!拒否はできる?

離婚して子供の親権を獲得した人が、元配偶者から「子供と会いたい」と言われたとき、その申し出を拒否することはできるのでしょうか。
非親権者(親権を失った親)には面会交流権があるため、離婚後も自分の子供と会うことができます。
そのため、親権者は非親権者と子供の面会交流を拒否することができないのが原則です。
しかし、これはあくまで原則の話ですので、子供の福祉に合致しない場合は、例外として面会交流権が制限され、親権者は別れた配偶者と子供の面会を阻止できます。
この記事では、面会交流権の原則と例外について解説します。
さまざまな事情で面会交流を拒絶したいと考えている人だけでなく、面会交流を拒絶された人も最後までお読みください。
- 目次
面会交流権とは?

面会交流権は、子供のいる夫婦が別居したり離婚したりしたときに、子供と暮らしていないほうの親(非親権者)に発生する権利で、離れて暮らしていても自分の子供と会うことができる権利です。
以下で詳しく解説します。
法律によって定められている面会交流権
面会交流権は民法第766条で定められています。 同条は、「父母が離婚したら、父と子、または母と子の面会交流方法を協議によって定めること」としています。
離婚後の子の監護に関する事項の定め等
第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
日本では、離婚をすると父母のどちらかが子供の親権を得て、他方が親権を失うことになります。
両親の離婚後、子供は親権を獲得した親と暮らすことになります。しかし、子供の成長や教育には、親権を失った親との交流も必要と考えられています。
そこで面会交流権を設定し、親権を失っても子供と会えるようにしたのです。
ここで監護権について解説しておきます。監護権は子供を育てる権利と義務を有した権利で、親権の一部です。
一般的には「親権者=監護権者」となりますが、経済力がある父親が親権者になり、子育てが得意な母親が監護権者になることもあります。
親権者と監護者が異なる離婚の場合、子供は監護権者と住むことになるため、親権者に面会交流権が発生します。
この記事内では「親権者=監護権者」として解説しています。
面会交流は離婚前の別居中も認められる
面会交流権は、元夫婦の2人が協議を行い、面会交流の方法を具体的に定めることで効力を発揮します。
なお、この面会交流に関する協議は、離婚前、離婚協議中、離婚後、いずれで行ってもかまいません。
離婚前の別居中であっても、面会交流権は発生します。
例えば、離婚せず別居が続いている場合、子供と一緒に暮らしていない親が面会交流権に関する協議を離婚前に請求することができます。
結婚していないが認知をした子供に対しても認められる
面会交流権は、結婚も離婚もしていない、認知のみ行った父親にも発生します。
例えば不倫相手の女性との間に子供をつくった男性が認知した場合、その男性に面会交流権が発生します。
面会交流の内容・決め方
面会交流で決める内容と、面会交流の決め方について解説します。
面会交流で決める内容
法律は面会交流の内容を定めていないため、当事者間で自由に決めて良いものですが、以下の内容を定めることが多いです。
- 日時や頻度
- 1回の面会交流の時間
- 面会交流する場所
- 子供の引き渡し方法
- 面会交流以外の交流
- 元の夫婦間の連絡方法
泥沼離婚のすえに親権を勝ち取った親は、なるべく面会交流の内容を狭めたいと考えるかもしれません。
しかし、面会交流権は子供の健やかな発育を実現するための権利です。
元の夫婦間の憎悪はいったん脇に置き、次に示すような子供に関する項目を軸に協議を行いましょう。
- 子供の精神状態
- 子供の希望
- 子供のしつけや教育
- 子供の年齢
面会交流権を行使する側の親は、なるべく緩やかな条件を提示したほうが良いでしょう。そうすることで「ルール違反」を防ぐことにつながります。
なお、やむを得ずルールを守ることができなくなったときの「特別ルール」を定めておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
面会交流の決め方
面会交流に関する協議は、基本的には元の夫婦が面談で行いますが、双方とも弁護士などの代理人を立てることもできます。
双方で合意した内容は、口頭で確認し合うだけでも良いのですが、合意書などの文書を作成するほうがルールを厳守しやすくなります。
なお、合意書は任意のものではなく、公証役場に行き、公正証書にすることで効果が強まります。
双方の意見が対立して面会交流の内容が決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停は調停委員という第三者が入るため、双方が落としどころを見つけやすくなります。 合意した内容は調停調書に記されるため、効果が高まります。
面会交流を拒絶する事はできる?
面会交流の内容を定めたあと、「やはり子供を会わせたくない」「面会交流の調整をするのがストレス」と親権者が思っても、原則として面会交流を拒絶することはできません。
しかし、例外的に面会交流の拒絶が可能になるケースがあります。 面会交流の拒絶が可能なケースと注意点を解説します。
離婚した相手との面会交流の調整をしたくない場合は?
例え面会交流権の行使であろうと、親権者が元の配偶者と話したくないと考えるのは自然なことです。もちろん相手側も同じように感じていることもあるでしょう。
この場合、双方の親族が面会交流の調整を行うことができます。
子供が面会交流を拒絶している
面会交流が設定された場合でも、子供の都合がつかなかったり、子供が嫌がったりした場合は、親権者は面会交流を拒絶できます。
子供が病気になった場合は面会交流の期日でも拒絶できます。ただその場合、代替日を設定する必要があるでしょう。
また、15歳以上で自分の意見をはっきり言える状態にある子供が、「親権のない親と会いたくない」と主張した場合は、面会交流を拒絶できます。
養育費の未払いを理由に拒否することはできない
非親権者から養育費を受け取っている親権者が、養育費の支払いが滞っていることを理由に面会交流を拒否することはできません。
逆に、正当な理由で面会交流が制限されている場合、面会交流の制限を理由に非親権者が養育費の支払いを止めることも許されていません。
養育費と面会交流はまったく別の問題であり、養育費を面会交流の条件にすることはできないのです。
面会交流の相手方が有責配偶者だった
両親がどのような理由で離婚したのかということは子供に関係ありません。
不倫やモラハラなど、非親権者が離婚理由を作った(有責配偶者であった)場合であっても、非親権者には子供と面会交流をする権利があります。
もちろん、面会交流によって子供の福祉に反する恐れがあるケースでは面会交流を拒否できる可能性があります。
これは、親権者が有責配偶者であった場合も同様です。 面会交流では子供の福祉と両親の離婚はわけて考えるのが基本になります。
面会交流の相手方が親権者にモラハラをする
非親権者がモラハラ行為をする場合、面会交流の連絡時、親権者に対してモラハラ行為を行う可能性があります。
前述のとおり、両親の離婚理由は子供には関係ありません。そのため、両親の間でモラハラ行為があるという理由だけではで面会交流を拒絶することはできません。
しかし、両親のモラハラやDVを見ることは面前DVと言い、子供の精神に悪影響をおよぼす恐れがあります。
また、面会交流の連絡で口論になっている場合も子供は負担を感じてしまいます。
子供が直接モラハラ行為を見聞きしない場合であっても、面会交流の連絡を取り合うことで親権者が精神的に不安定になる場合は子供の養育に影響を及ぼす恐れがあります。
離婚理由と子供は関係しないというのが基本ですが、「モラハラ行為が子供の福祉に反する」と判断された場合は面会交流を拒絶することが認められる可能性があります。
面会交流を禁止、または制限すべきケースは?
子供への不利益が大きいと判断された場合、非親権者(子供と同居していない親)の面会交流権は制限されます。
一度面会交流が始まっていても禁止されることもあります。どのようなケースがあるのかご紹介します。
面会交流が禁止・制限される具体的なケースは?
次のような場合、面会交流が禁止されたり制限されたりします。
- 子供に暴力をふるう可能性がある
- 面会交流が親権者に大きな精神的負担を与え、それが子供の福祉を害する恐れがある
- 子供を連れ去る危険がある
- 子供と暮らす親を貶める可能性がある
- 親権者が再婚し子供がその新しい親を慕っている
これらはいずれも「子供のためにならない」という点で一致しています。
面会交流が認められないと判断される要因は?
家庭裁判所は、面会交流が子供の福祉に合わないと判断した場合非親権者の面会交流権を認めないことがあります。なお、子供の福祉は、次の7つの観点で検討されます。
- 子供の意見
- 子供の生活環境への影響
- 親権者の意見
- 親権者の養育や監護への影響
- 同居していない親の問題点
- 元夫婦が離婚にいたった経緯
- 元夫婦の離婚後の状態
面会交流の対象となる子供は未成年です。
未成年の子供は精神面で同居親(親権者)に多くを依存しています。そのため「子供の福祉の観点」といっても、親権者(同居している親)への影響を配慮している可能性があります。
一方的に面会交流を拒否する問題点
親権者が正当な理由なく一方的に面会交流を拒否することはできません。
なお、家庭裁判所の調停で非親権者に面会交流権が認められ、面会交流の内容が確定した場合、親権者は面会交流が円滑に進むよう協力する必要があります。
履行勧告されることも
家庭裁判所での調停を経て面会交流が設定されたにも関わらず、親権者が正当な理由なく面会交流を妨害すれば、家庭裁判所が親権者に対し面会交流を履行するよう勧告することがあります。
ただし、履行勧告は「調停で取り決めたことを守ってください」と言うだけですので、強制力はありません。
強制執行の可能性も
親権者が家庭裁判所の履行勧告や調停内容を無視した場合、強制執行という措置が取られます。
強制執行とはいえ、家庭裁判所の職員が子供を強制的に連れ出すことはできないため、間接強制という手段を取ります。
間接強制は、「履行勧告を無視して会わせない場合は、制裁金5万円を科す」といった内容になります。
慰謝料や罰金を請求されることも
親権者が面会交流の強制執行まで妨害した場合、罰金を科されたり、非親権者(面会交流を妨害された親)から慰謝料を請求されたりすることもあります。
面会交流を拒否するために取りたい対策
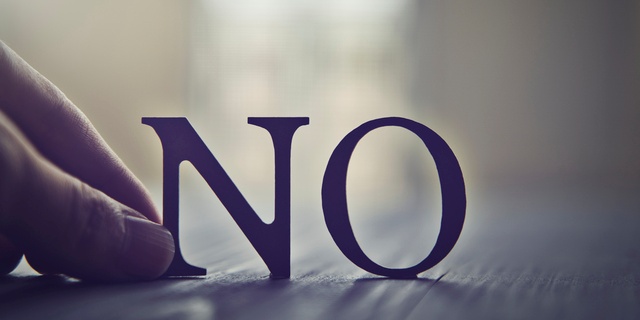
面会交流の拒否では、「拒否が子供の福祉に合致する」ケースと「拒否が子供の福祉に反する」ケースの2つのことが起こり得ます。
これは「子供の福祉にとって何が良いのか」を判断することの難しさを物語っています。
一見すると「面会交流は子供の福祉に合致する」と思われるときでも、長期間にわたって一緒に暮らしている親権者だからこそ「面会交流が子供の福祉に合致していない」とわかる場合があります。
このとき、面会交流を拒否するための最も有力な手段は、親権者が家庭裁判所に「合理的に」「冷静に」「段取りを踏んで」説明することです。
感情的に「元配偶者は子供に悪影響を与える」と強く主張しても、家庭裁判所は納得しません。家庭裁判所が納得すれば、あらためて面会交流を拒否することができます。
また、親権者は、元の配偶者から面会交流権をはく奪することの重大性を忘れてはなりません。子供にとっては離婚しても両親は両親です。
面会交流の阻止は、子供を親から引き離すことになります。それでも面会交流を拒否しなければならない理由があるのであれば、家庭裁判所も力になってくれるはずです。
なお、一般の人が家庭裁判所に「合理的」「冷静に」「段取りを踏んで」説明することは容易ではありません。
特に子供への影響が心配されるケースでは弁護士の力を借りることを強くおすすめします。
面会交流は誰のためにある権利なのか
今一度、面会交流権は誰のためにあるのか親権者も非親権者も考えましょう。
面会交流権は子供のためにあります。もちろん、非親権者の「子供に会いたい」という欲求を満たすことができる権利でもあるのですが、それは2次的、3次的なものと考えましょう。
面会交流を求める非親権者は、親権者に対し「自分の面会交流がなぜ子供の福祉に貢献するのか」を誠意をもって説明しましょう。
もし子供の成長にメリットがあるとわかれば、親権者は面会交流を拒否しないでしょう。
面会交流を拒否する親権者も、非親権者に「なぜあなたの面会交流が子供の成長に悪影響をおよぼすのか」を説明しましょう。
例えば、「ストレスを与えたくないから、中学受験が終わるまで面会交流を遠慮してほしい。その代わり、合格したら旅行に連れて行ってほしい」と伝えれば、非親権者も協力してくれるはずです。
両親が離婚したという事実だけで子供は大きなストレスを抱えています。それに加えて面会交流で両親がさらにもめれば、子供の心は余計に傷つくことになります。
まとめ
面会交流の問題は、子供の精神面に大きな影響を与えます。
親は自分たちの「会わせたくない感情」と「会いたい感情」をひとまず脇に置き、面会交流することのメリットとデメリットを話し合いましょう。
しかし、離婚した者同士が、ネガティブな感情を押し殺して冷静に判断することは容易ではありません。面会交流について悩んだら、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は第三者の立場で子供の将来を踏まえた提案をしてくれます。また弁護士に依頼すれば、面会交流を取り決めた内容とおりに進めやすくなります。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載していいます。ぜひお役立てください。
関連記事≫≫
離婚に強い弁護士の選び方って?弁護士選びで失敗しないポイント。
子供への虐待を理由に離婚できる?児童虐待から子供を守る方法とは。
都道府県から弁護士を検索する
離婚コラム検索
離婚の親権・養育費のよく読まれているコラム
-
 1位親権・養育費弁護士監修2020.03.30養育費を払わない方法|払えない・払いたくないなら知るべき7つのこと子供を持つ夫婦が離婚すると、親権を持たない親は親権者に対して養育費を支払う必要が...
1位親権・養育費弁護士監修2020.03.30養育費を払わない方法|払えない・払いたくないなら知るべき7つのこと子供を持つ夫婦が離婚すると、親権を持たない親は親権者に対して養育費を支払う必要が... -
 2位親権・養育費弁護士監修2019.02.28離婚後に扶養控除はどうなる?子供がいる場合の扶養手続き専業主婦やパートタイマーなどをしていて子供と夫の扶養に入っている人も多いでしょう...
2位親権・養育費弁護士監修2019.02.28離婚後に扶養控除はどうなる?子供がいる場合の扶養手続き専業主婦やパートタイマーなどをしていて子供と夫の扶養に入っている人も多いでしょう... -
 3位親権・養育費弁護士監修2019.07.29子連れ再婚|子供を連れて幸せな再婚をするために知るべき7つのこと1人で子供を育てていると、心細くなったり、誰かに支えてもらいたいと思ったりするこ...
3位親権・養育費弁護士監修2019.07.29子連れ再婚|子供を連れて幸せな再婚をするために知るべき7つのこと1人で子供を育てていると、心細くなったり、誰かに支えてもらいたいと思ったりするこ... -
 4位親権・養育費弁護士監修2019.01.15離婚後に子供を元配偶者と面会させたくない!拒否はできる?離婚して子供の親権を獲得した人が、元配偶者から「子供と会いたい」と言われたとき、...
4位親権・養育費弁護士監修2019.01.15離婚後に子供を元配偶者と面会させたくない!拒否はできる?離婚して子供の親権を獲得した人が、元配偶者から「子供と会いたい」と言われたとき、... -
 5位親権・養育費弁護士監修2019.01.10親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?子供を持つ夫婦が離婚する際に問題になるのは親権者指定です。親権獲得は母親のほうが...
5位親権・養育費弁護士監修2019.01.10親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?子供を持つ夫婦が離婚する際に問題になるのは親権者指定です。親権獲得は母親のほうが...
新着離婚コラム
-
 その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み...
その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み... -
 親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の...
親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の... -
 DV・モラハラ2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?...
DV・モラハラ2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?... -
 裁判・調停2025.05.02離婚の調停調書の効力とは?公正証書との違いや確認すべきポイント離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は...
裁判・調停2025.05.02離婚の調停調書の効力とは?公正証書との違いや確認すべきポイント離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は... -
 不貞行為弁護士監修2025.04.07PTA内で不倫が起きたら?チェックポイントと離婚・慰謝料請求の注意点PTAは「Parent(=親)」「Teacher(=先生)」「Associati...
不貞行為弁護士監修2025.04.07PTA内で不倫が起きたら?チェックポイントと離婚・慰謝料請求の注意点PTAは「Parent(=親)」「Teacher(=先生)」「Associati...
離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!
離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!
離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。
離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!
離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。













