離婚届は代筆できる?相手の同意なしで離婚する方法と代筆時の注意点

協議離婚では当事者双方が離婚について合意し、離婚届を役所に提出、受理されれば離婚が成立します。
離婚届には夫婦それぞれの署名欄があり、署名は当事者本人が自署します。しかし、身体が不自由で署名できない、あるいは署名したくないというケースもあるでしょう。
このような場合、あなたの代わりに相手方、あるいは第三者が離婚届に代筆することができるのでしょうか。
この記事では離婚届は代筆できるのか、相手方の同意を得ずに離婚届に代筆・提出した場合どうなるのか、相手方が離婚に同意しない場合の対処法について解説します。
- 目次
配偶者の同意があれば代筆した離婚届は有効
離婚届には「届出人署名押印」欄があります。協議離婚では、原則として届出人本人による自署となっています。
ただし、戸籍法施行規則第62条によれば、署名することができないと市町村長において認めるときは届出人の署名を代筆できるとされています。
また、離婚届に代筆する際は代筆理由を書く必要があります。
戸籍法施行規則第62条
届出人、申請人その他の者が、署名すべき場合に、署名することができないと市町村長において認めるときは、氏名を代書させるだけで足りる。
2 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
なお、離婚届に代筆する人についての制限はなく、委任状も必要ありません。
ただし、離婚届の提出まで代行してもらう場合は窓口で届出人の身分を確認されます。離婚届の受理証明書や離婚したことが記載された戸籍が欲しい場合は委任状が必要です。
配偶者の同意を得ず離婚届に代筆した場合
離婚が認められるためには以下の2つの要件が揃う必要があります。(民法第764条・同第739条・戸籍法第76条)
- 夫婦双方が離婚に合意しているという離婚の意思
- 離婚届の提出
離婚届の届出人の代筆には同意が必要です。
配偶者の同意を得ず、離婚届に代筆し、役所へ勝手に提出した場合、離婚の意思が欠けていることになり、離婚は無効となります。
離婚の意思はあるものの、代筆の同意がないという場合も同様に無効となります。ただし、相手方が離婚について追認(遡って事実を認めること)すれば離婚は成立します。
偽造した離婚届の作成・提出は刑事罰に問われる
相手の同意を得ずに離婚届に代筆した場合、刑事罰に問われる可能性があります。
同意を得ずに離婚届の相手の氏名を代筆した場合、有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)に問われる恐れがあります。
また、偽造した離婚届を役所へ提出すれば偽造有印私文書行使罪(刑法第161条1項)に問われます。
なお、偽造した離婚届が受理された場合、市役所に虚偽の届出を行い、戸籍に不実の事実を記載させたとして、公正証書原本不実記載罪(刑法第157条1項)に問われる恐れあります。
慰謝料請求される可能性がある
偽装した離婚届を役所へ提出した場合、相手方から慰謝料請求される恐れがあります。
本来ならスムーズに進むはずだった離婚手続きが拗れてしまい、長期化する可能性があります。
少しでも早く離婚を成立させたいのであれば、逸る気持ちは抑え、順を追って離婚を進めていきましょう。
代筆で離婚届を書く際の注意点
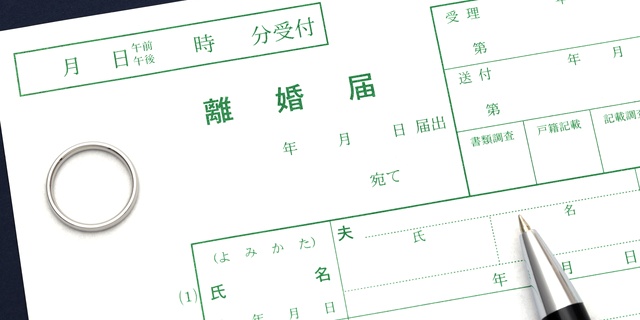
離婚届に代筆する際は以下の点に注意しましょう。
- 代筆の合意した内容を書面で残しておく
- 証人欄は代筆不可
- 合意がなくても離婚届が受理される可能性がある
それぞれについて詳しく解説します。
代筆に合意した内容を書面で残しておく
離婚届の代筆の有無については、後になってトラブルに発展する恐れがあります。相手方が代筆に同意した内容を書面で残しておきましょう。
合意書を作成していない場合は相手方が代筆に同意した内容のメールなどを保存しておきましょう。
証人欄は代筆不可
民法第739条で婚姻時には二人の証人が必要であることを定めており、この規定は民法第764条により離婚にも準用されます。
協議離婚の場合、離婚届には届出人だけでなく、証人欄に署名が必要です。
民法第739条(婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
民法第764条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
相手方の同意があれば届出人の代筆は可能ですが、証人欄の代筆は認められていません。必ず証人本人に自署してもらいましょう。
証人は18歳以上の人であれば誰でもかまいません。どうしても証人を頼める人がいない場合は代行サービスや弁護士への依頼を検討すると良いでしょう。
合意がなくても離婚届が受理される可能性がある
相手方の合意を得ずに代筆・提出された離婚届は無効です。しかし、形式上は離婚届が受理され、離婚が成立する可能性があります。
成立した離婚を無効にする場合、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申立てる必要があります。
なお、離婚成立後に再婚していた場合、離婚が無効となることで重婚状態になります。
民法第732条では重婚は禁止されているため、重婚禁止に違反した倍は当事者や親族、検察官が取り消し請求を行うことができます。(民法第744条)
民法第732条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
民法第744条(不適法な婚姻の取消し)
第731条、第732条及び第734条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
配偶者が離婚に同意しない場合の対処法

法定離婚事由があれば、裁判で離婚が認められる可能性があります。法定離婚事由とは以下の5つです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大事由
法定離婚事由があることを立証できれば、配偶者の合意がなくても、裁判で離婚が認められる可能性があります。
なお、2024年5月に民法改正が成立し、4号の「回復の見込みがない強度の精神病」が法定離婚事由から削除されました。
この改正は2024年5月24日に公布されており、公布から2年以内には施行されることになります。
弁護士に交渉を依頼する
離婚届の代筆は双方が離婚に合意しているという前提で認められています。相手方が離婚に合意していないのに離婚届に代筆すると離婚は無効になります。
また、刑事罰に問われたり、損害賠償請求される恐れもあります。
当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、話が拗れてしまうケースもあります。
配偶者から離婚の合意が得られないという場合は弁護士に交渉を依頼し、間に入ってもらうことで話し合いが進みやすくなります。
まとめ
届出人の同意があれば離婚届に代筆することは可能です。
しかし、同意が得られない状態で勝手に代筆すると離婚は無効になりますし、刑事罰に問われたり、損害賠償を請求される恐れがあります。
相手方が離婚に合意しない場合は弁護士に交渉を依頼することで話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚・男女問題に強い弁護士のポータルサイトです。ぜひお役立てください。
都道府県から弁護士を検索する
離婚コラム検索
離婚の基礎知識のよく読まれているコラム
-
 1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ...
1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ... -
 2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです...
2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです... -
 3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と...
3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と... -
 4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚...
4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚... -
 5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...
5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...
新着離婚コラム
-
 DV・モラハラ2026.01.21エネ夫の特徴と対策|妻を追い詰める正体と法的解決へのステップエネ夫(エネミー夫)という言葉を聞いたことはありますか?「味方であるはずの夫が、...
DV・モラハラ2026.01.21エネ夫の特徴と対策|妻を追い詰める正体と法的解決へのステップエネ夫(エネミー夫)という言葉を聞いたことはありますか?「味方であるはずの夫が、... -
 基礎知識2026.01.08婚前契約(プレナップ)の全て|メリット・デメリット・有効な書き方婚前契約と聞いてどのようなイメージを持ちますか?人によっては「離婚を意識している...
基礎知識2026.01.08婚前契約(プレナップ)の全て|メリット・デメリット・有効な書き方婚前契約と聞いてどのようなイメージを持ちますか?人によっては「離婚を意識している... -
 親権・養育費弁護士監修2025.12.08【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。しかし、「養育費だ...
親権・養育費弁護士監修2025.12.08【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。しかし、「養育費だ... -
 親権・養育費弁護士監修2025.11.17離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。面会交流...
親権・養育費弁護士監修2025.11.17離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。面会交流... -
 不貞行為弁護士監修2025.10.31不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド配偶者に不倫された!「不倫相手と別れさせたい」「配偶者は『もう別れた』と言ってい...
不貞行為弁護士監修2025.10.31不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド配偶者に不倫された!「不倫相手と別れさせたい」「配偶者は『もう別れた』と言ってい...
離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!
離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!
離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。
離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!
離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。












