自己破産時の養育費の扱いは?手続き前後の扱いと払えない時の対処法

子供がいる夫婦が離婚すると、子供と離れて暮らす側の親は養育費支払い義務を負います。
しかし、何等かの事情で、養育費を支払う側から「自己破産したから払えない」と言われた場合、どう対応すれば良いのでしょうか。
この記事を最後まで読むことで以下のことがわかります。
・自己破産すると養育費は免責されるのか
・養育費を支払えないほど困窮している場合に起こること
・養育費を支払えない場合の対処法
・自己破産前、手続き中、自己破産後の養育費の扱いについて
・自己破産後の養育費の支払い方法
・受け取る側が知っておくべきこと
- 目次
自己破産とは
自己破産とは、借金の返済ができない状態になった際に行う債務整理の種類のひとつです。
具体的には裁判所に破産申立書を提出し、借金を返す能力がないことを認めてもらい、すべての返済義務をなくす手続きになります。
なお、「借金の返済ができない状態」とは、自分が今持っている財産やこれから得られる収入を総合的に鑑みて、すべての債務を返済できないと考えられる状態を言います。
自己破産を行うことで、債務者(借金をした人)は自分の財産を処分し、債権者(お金を貸した側)に対して公平に分配する必要があります。
自己破産しても養育費は免責されない
借金の返済義務を免除することを免責と言います。
自己破産すればどんな債務も免責されるわけではありません。
破産法では、自己破産しても養育費は免責されないと定められているため、自己破産後も支払い義務が残ります。
破産法第253条(免責許可の決定の効力等)
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
4 次に掲げる義務に係る請求権
ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
なお、非免責債権には以下のようなものがあります。
- 租税等(税金や健康保険料、下水道料金など)の請求権
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 婚姻費用や養育費など親族関係に係る請求権
- 使用人の請求権・預り金返還請求権 (雇用主の場合)
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- (交通事故や刑事事件など)罰金等の請求権
養育費を支払えないほど困窮している場合に起こりうること

養育費を支払えないほど困窮している場合に起こりうることとして以下のようなものがあります。
- 養育費請求調停を申し立てられる
- 財産の差し押さえ
- 遅延損害金が発生する
それぞれについて下記で解説します。
養育費請求調停を申し立てられる
離婚時に養育費を口約束で取り決めただけの場合や離婚協議書を公正証書にしていなかった場合、養育費を受け取る側から養育費請求調停を申し立てられる可能性があります。
調停は裁判所の手続きですが、あくまで話し合いによって合意を図る手続きです。
支払う側の経済状況を踏まえ、調停委員から妥当な金額が提案される可能性があります。
調停で話がまとまらない場合は審判に移行し、裁判所が養育費の金額について判断することになります。
財産の差し押さえ
離婚調停や審判が成立すると調停調書や審判書、また裁判に進んだ場合は判決書が作成されます。
これらの書類には執行力があるため、養育費の未払いが続くと財産が差し押さえられる可能性があります。
離婚時に強制執行認諾文言付きの公正証書を作成して養育費の支払いを取り決めている場合も、未払いが続くと財産を差し押さえられる可能性があります。
遅延損害金が発生する
養育費の支払いが滞った場合、遅延損害金が加算される可能性があります。 遅延損害金とは金銭債務の支払いが遅延したことに対する損害賠償金です。
債務不履行により、債権者(養育費を受け取る側)に損害が生じると、債務者(養育費を支払う側)は本来の債務の履行に加えて、債権者の損害を賠償する必要があります(民法第415条第1項)。
養育費の遅延損害金の利率について、当事者間で取り決めがある場合はその利率に従って計算します。
一方、当事者間で遅延損害金について取り決めをしていない場合は法定利率で計算することになります。 (民法第419条第1項)。
なお、養育費の遅延損害金には法的に定められた上限はありません。
しかし、不当に高い利率で遅延損害金を定めた場合は公序良俗違反によって無効になる可能性もあります(民法第90条)。
養育費を支払えない場合の対処法
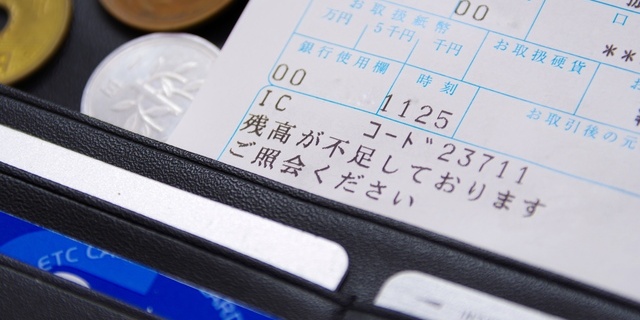
生活が困窮し、養育費を支払えない場合の対処法として、養育費の減額請求があります。
養育費を減額請求する方法としては以下の2つがあります。
- 元配偶者と減額交渉を行う
- 家庭裁判所の養育費減額請求調停を申し立てる
① の場合、相手方と合意ができれば、減額してもらえます。
しかし、養育費を受け取る側としては減額請求に応じると収入が減ることになるため、拒否されることもあります。
このような場合は➁の養育費減額請求調停を申し立てることになります。なお、養育費の減額請求は破産手続き中でも可能です。
どのような手順・方法で行えば良いかについては弁護士にご相談ください。
養育費の減額請求が認められる可能性があるケース
養育費の減額が認められる可能性があるケースとしては以下のようなものがあります。
- 支払い義務者の収入が、やむを得ない事情で減った
- 支払い義務者が再婚し、扶養家族が増えた
- 支払い義務者が再婚相手の連れ子と養子縁組をした
- 受け取る側の収入が増額した 受け取る側が再婚し、子供が再婚相手と養子縁組をした
一方、「養育費を払いたくない」「養育費の額が高いことに気づいた」という理由では認められない可能性が高いです。
養育費の支払いが困難になったときの対処法は以下の記事も参考にしてください。
自己破産前の養育費の扱いについて
ここからは自己破産手続き前の養育費の注意点について解説します。
滞納した養育費はどうなるのか
自己破産手続き前にすでに滞納している養育費がある場合、債務のひとつとして取り扱われ、自己破産手続きの対象になります。
基本的に破産者に財産があれば、破産管財人により財産の処分と現金化(換価)が行われ、債権額の割合に応じて債権者に配当されることになります。
このとき、養育費だからという理由で特別扱いされることはなく、他の債権者と同様に債権額に応じた分配を受けることになります。
しかし、破産者には財産がほとんど残っていないことが多く、配当されるのはごくわずかであることが多いです。
配当分から未払いの養育費を差し引いてもマイナスが多い場合は、自己破産後に改めて養育費を請求される可能性があります。
滞納した養育費を支払ってはいけない
「子供のために滞納していた養育費を払いたい」
「元配偶者から催促されている」
このような理由により、自己破産前に未払いの養育費を支払おうとするケースがあります。
しかし、滞納した養育費を自己破産前に支払うと偏頗(へんぱ)弁済とみなされる恐れがあります。
偏頗とは、不公平な偏りがあるということです。
偏頗弁済は、特定の債権者だけに弁済したり、担保を提供したりする行為です。個人再生や自己破産において、偏頗返済はNG行為とされています。
偏頗返済が発覚すると、免責が認められなくなる恐れがあります。
自己破産手続き中の養育費の扱いについて

次に自己破産手続き中の養育費の注意点について解説します。
滞納した養育費を支払うのはNG
自己破産手続き中も滞納した養育費を支払うと偏頗返済とみなされる可能性があります。
そのため、滞納した養育費を自己破産手続き中に支払ってはいけません。
滞納した養育費の支払いがNGとなるのは以下のいずれかの時点になります。
- 支払不能となった
- 破産手続き開始申立て後
① の支払不能となったときとは、返済能力がないことで支払い期限が到来した借金の返済ができなくなった状態を言います。
例えば、自己破産について弁護士に依頼した場合は、依頼後の養育費の支払いは偏頗返済とみなされる可能性があります。
なお、養育費請求側の経済状況が悪いなど、特別な事情がある場合は滞納養育費を支払うことができるケースもあります。
どのような場合に滞納した養育費の支払いが認められるかについて、個人で判断するのは困難です。弁護士にご相談ください。
手続き中の養育費は通常通り支払う
自己破産手続き開始後に支払期限が来る債権は自己破産手続きの対象外となります。
そのため、自己破産手続き中に支払期限が来る養育費については通常通り支払いましょう。
自己破産後の養育費の扱いについて
ここからは自己破産後の養育費の注意点について解説します。
自己破産後の養育費は通常どおり支払う
自己破産後に支払期限が来る養育費についても当然通常どおりに支払います。滞納した分についても、自己破産後は支払う必要があります。
破産手続き前や手続き中に請求側が配当を受けられなかった残額があれば、支払い義務者から請求される可能性があります。
破産手続開始決定後の強制執行について
自己破産後に養育費の支払いが滞った場合、再度支払いを請求されたり、差し押さえされたりする恐れがあります。
給与がある場合は給与の差し押さえを行うことが一般的です。
給与が差し押さえられると、裁判所から勤務先に通知が届くため、養育費を滞納している事実が勤務先にバレてしまいます。
特に養育費の取り決めについて公正証書を作成している場合は予期せぬ強制執行がなされる可能性があります。
自己破産を弁護士に依頼している場合は公正証書を作成していること、もしくは裁判の手続きで養育費を決めたことを弁護士に伝えておきましょう。
自己破産後の養育費の支払い方法

養育費の支払い方法を口座振り込みにしている場合、自己破産後は注意が必要です。
これを解説する前に、自己破産の2つの種類について把握しておきましょう。
- 管財事件: 破産者が所有する財産を破産管財人が現金化(換価処分)し、債権者へ公平に分配する手続き。破産者が一定以上の財産を持っていたり、免責不許可事由に該当していたりする場合に選択される。
- 同時廃止事件:破産管財人が選任されず、破産手続きが開始されると同時に破産事件を廃止する手続き。
なお、一定程度以上口座残高がある場合、①の管財事件として取り扱われる可能性があります。
どのくらいの残高がある場合に管財事件として取り扱われるかについては、申立を行う地方裁判所によって異なります。
この場合、破産管財人によって財産が換価処分されるため、預金が没収される可能性があります。
現金など自己破産の対象財産として処分されない財産があれば、そこから支払うなどの手段を検討しましょう。
【受け取る側向け】支払い義務者の自己破産と養育費の注意点
ここからは、養育費支払い義務者が自己破産した際に養育費を受け取る側が注意すべき点について解説します。
離婚時に養育費について取り決め、公正証書にしておく
離婚の際、養育費について取り決めた内容を公正証書にしておきましょう。
このとき、「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成することで、養育費の未払いが起きた際に速やかに相手方の財産を差し押さえできます。
自己破産手続き前や手続き中に強制執行を行うと失効となり、申立が無駄になる可能性があります。
相手方が自己破産したからといって養育費を受け取れなくなるとは限りません。
相手方の借金がなくなれば、自己破産後に養育費を支払ってもらえる可能性もあります。
養育費の請求には時効がある
未払いの養育費の請求権には時効があります。具体的には以下のとおりです。
- 協議離婚:受け取る側が養育費を請求できることを知ったときから5年、または行使できるときから10年(民法第166条)
- 調停・審判・裁判:10年(民法第169条)
時効が完成していた場合、その分の養育費については支払いを受けられない可能性があります。
強制執行は破産手続き後に
前述のとおり、自己破産前の未払い養育費に対して、強制執行を申し立てていた場合、破産手続き開始後に強制執行が失効になります(破産法第42条)。
申立を行っても無駄になる可能性があるということです。
強制執行を行う際は、相手方の財産の状況やタイミングなどを総合的に判断して行いましょう。
養育費減額請求に応じるかどうかについて
養育費支払い義務者が困窮している場合、養育費の減額を請求されることがあります。 養育費の減額に応じると受け取る側の収入が減ることになります。
一方、養育費減額に応じることで助成金や手当などの公的扶助が増額されることもあります。
どちらのほうが良いか総合的に鑑みて判断しましょう。
養育費を受け取る側が自己破産する場合

ここからは、養育費を受け取る側が自己破産した場合について解説します。
受け取る側が自己破産する際に未払いの養育費があれば、支払いの見込みがあるかどうかで自己破産の状況が変わる可能性があります。
受け取る側に一定以上の財産があるかどうか
受け取る側に一定以上の財産がない場合、同時廃止事件として扱われます。
同時廃止事件の場合、破産手続き開始決定時に所有していた財産は手元に残ることになります。
この場合、未払いの養育費を請求することも可能になります。
一方、一定以上の財産がある場合は管財事件になります。そのため、未払いの養育費も含めてすべての財産が破産管財人の管理処分対象となります。
養育費の支払いが見込めるかどうか
支払い義務者からの支払いが見込めない場合、支払いが見込めない理由を破産申立書に記載する必要があります。
管財人が「支払いが見込めない」と判断しない場合は、管財人が調査を行います。
破産管財人の調査により、未払いの養育費の支払いが見込めず、受け取る側の財産が一定以下であると判断された場合はこれ以上破産手続きを進める意味がなくなります。
そのため、破産手続きは途中で終了となります。これを異時廃止と言います。
一方、支払い義務者からの養育費の支払いが見込める場合は破産管財人の管理処分対象となります。
ただし、子供との生活を送ることが困難であると裁判所が認めた場合は最大99万円(現金含む)までの財産を手元に残すことができます。
また、生活が著しく困窮しているなど、差し迫った状況の場合は養育費を受け取ることができる場合があります。
どのような場合に養育費を受け取ることができるかについては弁護士にご相談ください。
なお、養育費の支払いを受ける場合は自己破産手続きを依頼した弁護士に伝えましょう。
養育費を黙って受け取り、使い込んだ場合、免責が認められなくなる可能性があります。
また、状況によっては破産詐欺罪に問われる恐れがあります。
まとめ
養育費の支払い義務は自己破産しても消えません。また、自己破産における養育費の取り扱いについて一般の方が判断するのは困難です。
養育費の未払いが起きたとき、養育費の支払い中の自己破産については弁護士に相談することをおすすめします。
離婚リンクでは、養育費や離婚問題について精通した弁護士を多数掲載しております。是非お役立てください。
都道府県から弁護士を検索する
離婚コラム検索
離婚の親権・養育費のよく読まれているコラム
-
 1位親権・養育費弁護士監修2020.03.30養育費を払わない方法|払えない・払いたくないなら知るべき7つのこと子供を持つ夫婦が離婚すると、親権を持たない親は親権者に対して養育費を支払う必要が...
1位親権・養育費弁護士監修2020.03.30養育費を払わない方法|払えない・払いたくないなら知るべき7つのこと子供を持つ夫婦が離婚すると、親権を持たない親は親権者に対して養育費を支払う必要が... -
 2位親権・養育費弁護士監修2019.02.28離婚後に扶養控除はどうなる?子供がいる場合の扶養手続き専業主婦やパートタイマーなどをしていて子供と夫の扶養に入っている人も多いでしょう...
2位親権・養育費弁護士監修2019.02.28離婚後に扶養控除はどうなる?子供がいる場合の扶養手続き専業主婦やパートタイマーなどをしていて子供と夫の扶養に入っている人も多いでしょう... -
 3位親権・養育費弁護士監修2019.07.29子連れ再婚|子供を連れて幸せな再婚をするために知るべき7つのこと1人で子供を育てていると、心細くなったり、誰かに支えてもらいたいと思ったりするこ...
3位親権・養育費弁護士監修2019.07.29子連れ再婚|子供を連れて幸せな再婚をするために知るべき7つのこと1人で子供を育てていると、心細くなったり、誰かに支えてもらいたいと思ったりするこ... -
 4位親権・養育費弁護士監修2019.01.15離婚後に子供を元配偶者と面会させたくない!拒否はできる?離婚して子供の親権を獲得した人が、元配偶者から「子供と会いたい」と言われたとき、...
4位親権・養育費弁護士監修2019.01.15離婚後に子供を元配偶者と面会させたくない!拒否はできる?離婚して子供の親権を獲得した人が、元配偶者から「子供と会いたい」と言われたとき、... -
 5位親権・養育費弁護士監修2019.01.10親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?子供を持つ夫婦が離婚する際に問題になるのは親権者指定です。親権獲得は母親のほうが...
5位親権・養育費弁護士監修2019.01.10親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?子供を持つ夫婦が離婚する際に問題になるのは親権者指定です。親権獲得は母親のほうが...
新着離婚コラム
-
 DV・モラハラ2026.01.21エネ夫の特徴と対策|妻を追い詰める正体と法的解決へのステップエネ夫(エネミー夫)という言葉を聞いたことはありますか?「味方であるはずの夫が、...
DV・モラハラ2026.01.21エネ夫の特徴と対策|妻を追い詰める正体と法的解決へのステップエネ夫(エネミー夫)という言葉を聞いたことはありますか?「味方であるはずの夫が、... -
 基礎知識2026.01.08婚前契約(プレナップ)の全て|メリット・デメリット・有効な書き方婚前契約と聞いてどのようなイメージを持ちますか?人によっては「離婚を意識している...
基礎知識2026.01.08婚前契約(プレナップ)の全て|メリット・デメリット・有効な書き方婚前契約と聞いてどのようなイメージを持ちますか?人によっては「離婚を意識している... -
 親権・養育費弁護士監修2025.12.08【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。しかし、「養育費だ...
親権・養育費弁護士監修2025.12.08【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。しかし、「養育費だ... -
 親権・養育費弁護士監修2025.11.17離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。面会交流...
親権・養育費弁護士監修2025.11.17離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。面会交流... -
 不貞行為弁護士監修2025.10.31不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド配偶者に不倫された!「不倫相手と別れさせたい」「配偶者は『もう別れた』と言ってい...
不貞行為弁護士監修2025.10.31不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド配偶者に不倫された!「不倫相手と別れさせたい」「配偶者は『もう別れた』と言ってい...
離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!
離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!
離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。
離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!
離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。












