強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説

認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の親子関係を成立させる手続きを言います。
しかし、子供ができたにも関わらず、交際中の相手が自発的に子供の認知してくれないこともあります。
このような場合に、裁判所の手続きによって強制的に認知を行うのが強制認知です。この記事を最後まで読むことで以下のことがわかります。
・強制認知の手続きの流れ
・認知の訴えができる人
・認知の訴えの期限
・強制認知をすべきケース
・強制認知の注意点
・DNA鑑定を拒否された場合の対処法
- 目次
強制認知とは
婚姻関係にない男性との間に生まれた子供について、父親と子供の間に法律上の親子関係が認められるためには、認知が必要です。
婚姻関係にある男女の間に生まれた子供は、戸籍上、男性の子供と扱われます。しかし、婚姻関係にない男女の場合、戸籍上の父子関係は確認できません。
このとき、男性が認知をすれば、父親の名前が戸籍に記載され、法的に父子関係が認められることになります。
ただし、父親が自発的に認知してくれるとは限りません。「責任を負いたくない」「既婚者である」などの理由で認知を拒むこともあります。
何もしなければ、戸籍の子供の父親の欄は空白のままとなり、父親が存在しないことになります。
このような場合に、母親または子供自身が家庭裁判所を通して父親に認知を強制させる手続きを強制認知と言います。
なお、認知は手続きの方法によって以下のような種類があります。
- 父親の意思に基づく認知:「任意認知」「遺言認知」「胎児認知」
- 裁判所による強制的に認知の効力が生じる:「強制認知」「死後認知」
それぞれ、以下のような違いがあります。
- 任意認知:認知届の提出により、自発的に父親が認知する手続き
- 遺言認知:何らかの事情で父親が生前に認知ができず、遺言によって父親の死後に効力が生じる認知手続き
- 胎児認知:子供が生まれる前に行う認知手続き
- 強制認知(裁判認知):父親が任意認知をしない場合に、調停や裁判所の決定などによって強制的に父親に認知を求める手続き
- 死後認知:認知をしてほしいものの、すでに父が死亡している場合に子供が裁判所に請求する認知手続き
以上をまとめたものが下記となります。
| 手続きの違い | 認知の種類 |
|---|---|
| 父親の意思に基づくもの | 任意認知 |
| 遺言認知 | |
| 胎児認知 | |
| 裁判所による強制的に認知の効力が生じるもの | 強制認知 |
| 死後認知 |
強制認知の手続きの流れ

強制認知の手続きの流れは以下のとおりです。
- 認知調停申立
- 認知の訴え
- 認知届の提出
それぞれについて順を追って解説します。
認知調停申立
強制認知を行うためにはまず、家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります。
家事事件は調停前置主義(家事事件手続法第257条1項)となっているため、訴訟の前に調停の申立てを行います。
申立先は相手方の住所地の家庭裁判所もしくは当事者が合意して決めた家庭裁判所になります。
認知調停を申し立てる際は以下の書類を家庭裁判所に提出します。
- 認知調停の申立書
- 子の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 収入印紙(1,200円分)
- 連絡用の郵便切手 ※申立先の裁判所によって金額が異なる
- 子の出生証明書写し及び母の戸籍謄本(全部事項証明書)※離婚後300日以内に出生した出生届未了の子に関する申立ての場合
なお、子と父の戸籍謄本については、申立後の提出でもかまいません。申立書は裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
調停では調停委員を介して話し合いを行い、認知について合意を図ります。父親が認知について合意すれば、家庭裁判所が必要な調査を行います。
認知の合意が正当であると判断されれば、合意に相当する審判(家事事件手続法第277条)がなされ、審判が確定すると認知の効力が生じます。
参考:裁判所「認知調停(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_18/index.html)」※1
認知の訴え
認知調停が不成立になった場合、家庭裁判所に対して認知の訴えを提起し、父子関係が認められるかどうかを争います。
認知の訴えに必要な書類は以下です。
- 訴状(正本、副本各1通)
- 主張を裏付ける証拠書類
- 収入印紙13,000円程度 ※裁判所に要確認
- 郵便切手代 ※申立先の裁判所によって金額が異なる
- 原告・被告・子供の戸籍謄本
- DNA鑑定代(10万円程度、必要な場合のみ)など
調停と異なり、裁判では、DNA鑑定などの生殖上の父子関係を明らかにするための手続きを行います。
手続きの結果を踏まえ、裁判所が父子関係の有無について判断をくだします。
判決が確定すると、その時点から、出生の時にさかのぼってその効力を生じます(民法第784条)。
なお、裁判に進んだ場合であっても当事者間で合意ができれば、和解を成立させることができます。
認知届の提出
審判確定日または判決確定日から10日以内に以下のいずれかの場所に認知届を提出します。
- 子または父親の本籍地を管轄する役所・役場
- 届出人の住所地を管轄する役所・役場
認知届の提出の際に必要な書類は以下となります。
- 認知届 ※役所の窓口で取得可能(役所のウェブサイトでダウンロードできるようになっている場合もあります)
- 届出人の本人確認書類:運転免許証、旅券(パスポート)など
- 裁判の謄本および確定証明書 ※事件を扱った家庭裁判所で取得可能
なお、認知の届出ができるのは認知調停の申立人・認知訴訟の原告になります。
認知の訴えができる人

認知の訴えは誰でもできるわけではありません。提訴権者は以下となります。
- 子供
- 子供の法定代理人(未成年の子の母親など)
- 子供の直系卑属(子の子、父からみた場合の孫・ひ孫など)
- 子供の直系卑属の法定代理人
認知の訴えの期限
認知の訴えには期限がありません。ただし、認知請求の相手方(父親)が死亡してから3年が経過すると、認知の訴えを提起できません。
また、子供が生まれる前(胎児)の段階では強制認知をさせることはできません。
強制認知をすべきケース
強制認知を検討すべきケースには以下のようなものがあります。
- 養育費がほしい
- 子供に相続権を与えたい
それぞれについて下記で解説します。
養育費がほしい
法律上の親子関係が成立すれば、父親に子供の間に扶養義務が生じます(民法第877条1項)。
なお、扶養義務とは、互いの生活を支え合う義務を言い、生活保持義務と生活扶助義務の2種類にわかれると解されています。
特に親が未成熟子に対して負う扶養義務は、親と同レベルの生活を保障しなければならないという強い義務(生活保持義務)になります。
そのため、強制認知が認められれば、父親に対して養育費の請求が可能になります。
子供に相続権を与えたい
法律上の親子関係があれば相続が発生します(民法第887条1項)。
そのため、強制認知が認められれば、子供は父親の相続人となり、父親が亡くなった際に財産を相続する権利が得られます。
ただし、相続する財産には借金やローンなどの負の財産も含まれます。
父親の経済状況によっては父親が子供に扶養を求めたり、借金を背負わされたりする恐れがあります。
父親の経済状況などを総合的に鑑みて、強制認知をすべきかどうか慎重に判断しましょう。
強制認知の注意点
強制認知を検討する際は以下の点に注意しましょう。
- 父親側との関係悪化
- 手続きの負担増
それぞれについて下記で解説します。
父親側との関係悪化
強制認知が認められれば、父と子の間に法律上の親子関係が生じます。
しかし、父親が認知に非協力的な状態だと、強制認知によって父親との関係性が悪化する可能性があります。
父親との関係性が悪化すれば、養育費の支払いや父子関係にも影響が出る恐れがあります。
手続きの負担増
強制認知は時間もお金もかかります。
裁判所には平日昼間に出向く必要があります。また、複雑な法的手続きや状況によってDNA鑑定を行う必要もあります。
そのため、精神的にも経済的にも負担が大きくなります。
DNA鑑定を拒否された場合
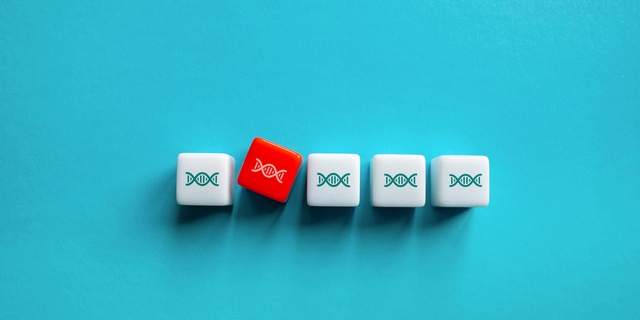
強制認知の証拠となるもののひとつにDNA鑑定があります。
DNA鑑定によって強制認知が認められれば、男性はその結果から逃れることはできません。そのため、男性がDNA鑑定やサンプルの提出を拒むケースもあります。
このような場合に備え、DNA鑑定を拒否された場合の注意点と対処法を解説します。
- 相手に無断でDNA鑑定をしてはいけない
- DVA鑑定のメリットを伝える
- DNA鑑定以外の証拠を集める
それぞれについて下記で解説します。
相手に無断でDNA鑑定をしてはいけない
「強制認知を拒まれた」「サンプル提出を拒まれた」という場合、無断で相手のサンプルを入手し、DNA鑑定をしようと考える方もいるかもしれません。
しかし、相手に無断でDNA鑑定を行う行為はプライバシーの侵害に該当する恐れがあります。
そのため、不法行為に基づく損害賠償を請求される可能性があります。
DVA鑑定のメリットを伝える
考え方によっては、DNA鑑定は男性側にもメリットがあります。
例えば、「親子関係がない」とわかれば、養育費の支払い義務が生じません。
男性側に「親子関係がない」という自信があるのであれば、DNA鑑定を受けたほうが良いということになります。
また、DNA鑑定を拒まれたからといって、強制認知ができなくなるわけではありません。
むしろ、DNA鑑定を拒む姿勢により、「親子関係があることを認めている」という印象を裁判官が抱く可能性もあります。
DNA鑑定以外の証拠を集める
前述のとおり、DNA鑑定を拒まれたからといって、強制認知ができないわけではありません。
相手方がDNA鑑定を拒んだ場合、最終的には裁判官が親子関係について判断することになります。
このとき、原告側がDNA鑑定以外の状況証拠を集め、親子関係を立証する必要があります。具体的な証拠の例としては以下のようなものがあります。
- 妊娠・出産前後に当事者間で交わしたメールやLINE、SNSの履歴
- 血液型に矛盾がないことを示すもの
- 妊娠時期に当該男性との性交渉を立証するもの
- 妊娠時期に当該男性以外との性交渉がないことを立証するもの など
具体的にどのような証拠を集めれば良いのかについては弁護士にご相談ください。
まとめ
強制認知は子供の法的な権利を確保するために重要な手続きです。しかし、状況によっては父親だけでなく、母親や子供にも負担が生じる恐れがあります。
強制認知は裁判所による手続きのため、専門知識が必要です。
強制認知を行うべきか、何から始めれば良いかなど、強制認知で悩んだら弁護士にご相談ください。
※1 裁判所「認知調停」
都道府県から弁護士を検索する
離婚コラム検索
離婚の親権・養育費のよく読まれているコラム
-
 1位親権・養育費弁護士監修2020.03.30養育費を払わない方法|払えない・払いたくないなら知るべき7つのこと子供を持つ夫婦が離婚すると、親権を持たない親は親権者に対して養育費を支払う必要が...
1位親権・養育費弁護士監修2020.03.30養育費を払わない方法|払えない・払いたくないなら知るべき7つのこと子供を持つ夫婦が離婚すると、親権を持たない親は親権者に対して養育費を支払う必要が... -
 2位親権・養育費弁護士監修2019.02.28離婚後に扶養控除はどうなる?子供がいる場合の扶養手続き専業主婦やパートタイマーなどをしていて子供と夫の扶養に入っている人も多いでしょう...
2位親権・養育費弁護士監修2019.02.28離婚後に扶養控除はどうなる?子供がいる場合の扶養手続き専業主婦やパートタイマーなどをしていて子供と夫の扶養に入っている人も多いでしょう... -
 3位親権・養育費弁護士監修2019.07.29子連れ再婚|子供を連れて幸せな再婚をするために知るべき7つのこと1人で子供を育てていると、心細くなったり、誰かに支えてもらいたいと思ったりするこ...
3位親権・養育費弁護士監修2019.07.29子連れ再婚|子供を連れて幸せな再婚をするために知るべき7つのこと1人で子供を育てていると、心細くなったり、誰かに支えてもらいたいと思ったりするこ... -
 4位親権・養育費弁護士監修2019.01.15離婚後に子供を元配偶者と面会させたくない!拒否はできる?離婚して子供の親権を獲得した人が、元配偶者から「子供と会いたい」と言われたとき、...
4位親権・養育費弁護士監修2019.01.15離婚後に子供を元配偶者と面会させたくない!拒否はできる?離婚して子供の親権を獲得した人が、元配偶者から「子供と会いたい」と言われたとき、... -
 5位親権・養育費弁護士監修2019.01.10親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?子供を持つ夫婦が離婚する際に問題になるのは親権者指定です。親権獲得は母親のほうが...
5位親権・養育費弁護士監修2019.01.10親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?子供を持つ夫婦が離婚する際に問題になるのは親権者指定です。親権獲得は母親のほうが...
新着離婚コラム
-
 DV・モラハラ2026.01.21エネ夫の特徴と対策|妻を追い詰める正体と法的解決へのステップエネ夫(エネミー夫)という言葉を聞いたことはありますか?「味方であるはずの夫が、...
DV・モラハラ2026.01.21エネ夫の特徴と対策|妻を追い詰める正体と法的解決へのステップエネ夫(エネミー夫)という言葉を聞いたことはありますか?「味方であるはずの夫が、... -
 基礎知識2026.01.08婚前契約(プレナップ)の全て|メリット・デメリット・有効な書き方婚前契約と聞いてどのようなイメージを持ちますか?人によっては「離婚を意識している...
基礎知識2026.01.08婚前契約(プレナップ)の全て|メリット・デメリット・有効な書き方婚前契約と聞いてどのようなイメージを持ちますか?人によっては「離婚を意識している... -
 親権・養育費弁護士監修2025.12.08【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。しかし、「養育費だ...
親権・養育費弁護士監修2025.12.08【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。しかし、「養育費だ... -
 親権・養育費弁護士監修2025.11.17離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。面会交流...
親権・養育費弁護士監修2025.11.17離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。面会交流... -
 不貞行為弁護士監修2025.10.31不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド配偶者に不倫された!「不倫相手と別れさせたい」「配偶者は『もう別れた』と言ってい...
不貞行為弁護士監修2025.10.31不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド配偶者に不倫された!「不倫相手と別れさせたい」「配偶者は『もう別れた』と言ってい...
離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!
離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!
離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。
離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!
離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。












