托卵妻と離婚できる?子供との親子関係や養育費、慰謝料について解説

子供と自分が似ていない…
性行為をした時期と出産時期が合わない…
このような場合、妻に托卵された可能性があります。
托卵とは、夫以外の男性との子供を夫に育てさせることを言います。
妻に托卵されたことが判明すれば、離婚を考えるかもしれません。また、「本当の子供ではないなら養育費を払いたくない」と思うこともあるでしょう。
この記事では、托卵妻と離婚する方法や親子関係の解消法、養育費の支払いを拒否する方法について解説します。
- 目次
托卵とは
托卵とは、実の親ではない人に自分の子供と信じ込ませ、子育てをさせることを言います。
托卵は元々ホトトギスやカッコウなどの鳥類に見られる習性で、ほかの鳥の巣に卵を産み付け、孵化したひな鳥をその鳥に育てさせることを言います。
これになぞらえ、妻が夫以外の男性との間にできた子供を夫の実子だと偽り、子育てを行うことを指します。托卵する女性のことを托卵女子、托卵妻と呼ぶこともあります。
托卵妻の割合
日本では托卵について詳しく調べたデータはありません。
一方、インターネットテレビ局ABEMAの報道番組ABEMA Prime出演のライター亀山氏は「何人かの産婦人科医に聞いたところ、(托卵妻の割合は)人が思っているよりずっと多い。6%から10%に行くかどうかといったところ」と述べています。
これは10~20人にひとりの割合で既婚女性が托卵をしているという計算になります。
参考:AbemaPrime「自分は不倫相手との子だった…“托卵妻”から生まれた当事者の苦悩 血液型検査で発覚「いきなり重たい十字架を背負わされた」海外では25人に1人の統計も(https://times.abema.tv/articles/-/10134190?page=1)」※1
托卵する目的
夫以外の男性との間にできた子供を夫の子だと偽って育てさせる理由には以下のようなものがあります。
- 不倫相手との子供が欲しい
- 結婚前の交際相手の子供を身ごもったまま今の夫と結婚してしまった
- 不倫による妊娠だが、離婚したくない など
「結婚前の妊娠が夫にバレることを避けたい」「不倫して妊娠してしまったが、生まれる子供は夫の子であれば都合がいい」と考えて托卵するケースが多いようです。
托卵妻と離婚する方法
托卵されたことを理由に離婚する方法について解説します。
- まずはDNA鑑定
- 親子関係をどうするか考える
- 妻と話し合う
- 話し合いがまとまらない場合は離婚調停・離婚訴訟
それぞれ順を追って解説します。
まずはDNA鑑定
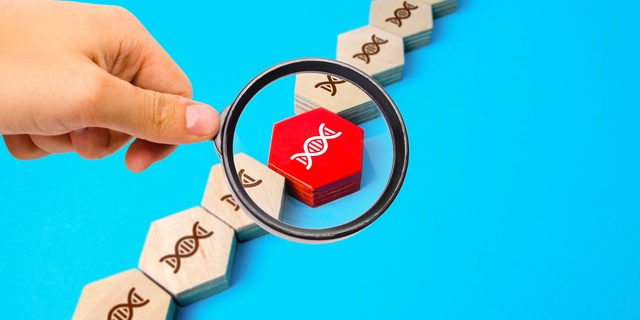
「自分の子供ではないかもしれない」 このようにお悩みなら、まずはDNA鑑定を依頼し、親子関係を調べましょう。
DNA鑑定とは自分と子供のDNA型を調査し、血縁的な親子関係があるかを分析する科学的手法です。
親子関係の存在が証明されれば、安心して子供を育て続けることができます。
DNA鑑定では、専用キットを使用し、綿棒のようなもので口腔内をこすり、付着した粘膜細胞を検査するというのが一般的です。
子供が使用したストローや歯ブラシ、おしゃぶりなどが使える場合もあります。
そのほか、DNA鑑定で用いるサンプルとしては以下のようなものがあります。
- 唾液
- 毛根のついた毛髪
- 血液
- 爪
- 歯 など
個人的な目的で使用する鑑定(私的検査)なら2~7万円程度で検査でき、1~3週間程度で結果が出ます。なお、費用や納期は検査機関によって異なります。
親子関係や離婚については、DNA鑑定で親子関係が否定されて初めて考えれば良いでしょう。
DNA鑑定は「DNA鑑定 親子」とウェブ検索すればDNA鑑定を行う業者がヒットします。
親子関係をどうするか考える
子供との間に親子関係がないことが判明したら、まずは親子関係をどうすうか考えましょう。実子でないとわかっても、愛情や絆があり、関係を絶とうと思えないかもしれません。
なお、血縁的に親子関係がないと判明しても、婚姻期間中に生まれた子供は夫の子と推定されます。
法律的には親子関係が存在することになるため、親子関係を解消しない限り扶養義務が生じ、養育費の支払い義務も発生します。
法的に親子関係を否定するためには嫡出否認と親子関係不存在確認の2つの方法があります。
これについては「養育費の支払いを拒否する方法」の項にて後述します。
妻と話し合う
子供との関係をどうするか決めたら、離婚について妻と話し合います。
話し合いで合意できればどのような理由でも離婚が認められます。これを協議離婚と言います。
協議離婚は当事者が話し合いで合意し、離婚届を役所に提出し、受理されれば成立します。
話し合いがまとまらない場合は離婚調停・離婚訴訟
話し合いで合意できない場合は家庭裁判所に離婚調停を申立てます。離婚調停でも合意ができなければ、離婚訴訟を提起します。
なお、裁判で離婚が認められるためには法定離婚事由が必要です。
夫の子供ではないことを知りながら夫の子供だと偽って子供を育てさせたことは、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまる可能性が高いです。
また、婚姻中に夫以外の男性との間に子供ができて出産した場合は不貞行為に該当します。 いずれの場合も裁判所が離婚を認める可能性が高いと言えます。
托卵されたら慰謝料請求が認められる可能性がある

婚姻中に不貞行為をしていた場合や、夫の子供ではないことを知りながら夫の子供だと偽って子育てをさせた場合、民法上の不法行為が成立します。
そのため、妻に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。
また、不倫は不倫をした妻と不倫相手による共同不法行為ですので、妻と不倫相手の2人に慰謝料を請求できます。
不貞行為が理由で離婚した場合の慰謝料相場は100~300万円です。
ただし、夫を騙して托卵していた場合、夫の精神的苦痛はより大きいと判断されやすく、より高額な慰謝料請求が認められる可能性があります。
何もしなければ養育費の支払い義務が生じる
托卵した妻との離婚が成立しても、法律上の親子関係を解消しない限り、離婚後も養育費の支払い義務が生じます。
法律上の親子関係を解消するためには次項で解説する法的手続きが必要です。
なお、DNA鑑定で親子関係がないと判明した場合であっても、法律上の親子関係を否定できるとは限りません。
養育費の支払いを拒否する方法
托卵妻からの養育費の支払い請求を拒否する方法は下記の4つです。
- 嫡出否認調停・訴訟
- 親子関係不存在確認調停・訴訟
- 子供の血縁上の父親に認知してもらう
- 妻に権利の濫用を主張する
嫡出とは婚姻関係にある男女から生まれることです。
血縁的な親子関係と法律上の親子関係が一致しないことを民法は認めています。
そのため、血縁的な親子関係がないからといって直ちに法律上の親子関係がないということにはなりません。
なお、嫡出否認訴訟・親子関係不存在確認訴訟のいずれもいきなり訴訟を起こすことができないため、まずは調停を申し立てる必要があります。
嫡出否認訴訟と親子関係不存在確認訴訟は同じようなものに思えるかもしれませんが、以下の点で違いがあります。
- 嫡出否認訴訟:法律上夫の子供であると推定される(嫡出が推定される)ケース
- 親子関係不存在確認訴訟:夫の子供であると推定されないケース
嫡出否認調停・訴訟

嫡出否認は嫡出推定される子供との親子関係を否定する手続きです。
「婚姻中に妊娠した妻が婚姻中に出産した」という場合は嫡出推定がおよびます。
しかし、今回のように「浮気相手の子供を妊娠して出産した。夫が親子関係を否定したい」という場合は嫡出否認を行うことになります。
夫が子供の出生を知ったときから3年以内に嫡出否認の訴えを提起することによって法律上の親子関係を否定することができます。
手順としては、まず家庭裁判所に嫡出否認調停を申し立て、当事者間で「夫の子ではない」ということについて合意を図ります。
合意ができた場合、裁判所がDNA鑑定の結果を踏まえ、その合意が正当なものだと認められれば、合意に沿った審判がなされ、夫と子供の親子関係は解消されます。
調停で合意できなかった場合は嫡出否認訴訟を提起し、裁判所が一切の事情を考慮して嫡出否認を認める判決がくだされれば、親子関係は否定されます。
民法改正前は「夫が子の出生を知ったときから1年」が申立期限でしたが、令和4年12月10日の民法改正により、3年に延長され、令和6年4月1日から施行されました。
また出訴権者も改正前は夫のみでしたが、改正後は父、子、母、前夫へと拡大されました。
親子関係不存在確認調停・訴訟
上記のように、嫡出否認の訴えができるケースは限定的です。そのため、それ以外のケースでは親子関係不存在確認訴訟を提起することになります。
親子関係不存在確認訴訟は以下のようなケースで親子関係を否定する手続きです。
婚姻前に妊娠した子供である 、婚姻中でも夫婦が会えない状況(海外出張・単身赴任・服役中・別居中など)で妊娠した子供等、嫡出子と推定されない子供との親子関係を否定する場合、親子関係不存在調停手続きにより親子関係を否定します。
手続きに期限はありません。
親子関係不存在確認の手続きについても、まずは調停を申し立て、当事者間で夫と子供が親子関係になることの合意を図ります。
合意できた場合、裁判所が必要な調査を行い、合意が正当だと認められれば合意に沿った審判がなされます。
調停の結果合意できなければ、親子関係不存在確認訴訟を提起します。裁判で夫が勝訴すれば親子関係が否定されます。
妻に権利の濫用を主張する
夫が子供の出生を知ってから3年が経過し、親子関係不存在確認の手続きを行っても、「嫡出否認の訴えと実質上同一」と判断されれば、訴えが却下される可能性があります。
このような場合、妻に対して権利の濫用を主張することで、養育費の支払いを拒否できる可能性があります。
権利の濫用とは、「権利の行使(この場合は妻からの養育費の支払い請求)ではあるが、社会常識や道徳に基づくと無効と判断するのが妥当な行為」を指します。
例えば、以下のような事情があれば、権利の濫用を主張することで養育費の支払いを拒否できる可能性があります。
- 夫の子供でないことを妻が知りながら夫に伝えなかったことで夫が親子関係を否定する手段を失ったこと
- 夫はこれまで十分な養育費を支払っていること
- 妻が子供を監護する費用を賄うことができ、子の福祉に反するとは言えないこと
認知請求が認められれば子供の実の父親に養育費を請求できる

子供の血縁上の父親に養育費を請求するためには、妻から子供の実の父親に認知請求を行い、認知が認められる必要があります。
そのためには、まず嫡出否認の訴え、あるいは親子関係不存在確認の訴えにより、法律上の親子関係を否定してもらう必要があります。
そのうえで、子供または妻(子供の法定代理人)が子供の実の父親に対して認知請求を行い、認知が認められれば、妻から子供の実の父親に対して養育費を請求できます。
まとめ
妻に托卵された、または托卵された可能性がある場合、まずはDNA鑑定を行い、子供との間に血縁上の親子関係がないかどうかを確認しましょう。
そのうえで、子供との親子関係をどうするかを考えます。 法律上の親子関係を否定しなければ、養育費の支払い義務が生じます。
法律上の親子関係を否定し、養育費の支払いを拒否したいなら、まずは弁護士に相談し、解決策についてアドバイスをもらうと良いでしょう。
※1 AbemaPrime「自分は不倫相手との子だった…“托卵妻”から生まれた当事者の苦悩 血液型検査で発覚「いきなり重たい十字架を背負わされた」海外では25人に1人の統計も」
都道府県から弁護士を検索する
離婚コラム検索
離婚のその他離婚理由のよく読まれているコラム
-
 1位その他離婚理由弁護士監修2019.07.25姑が嫌いすぎて我慢できない!嫁姑問題を理由に離婚できるのか夫はうまくやっているけれど、姑との折り合いが悪い… 嫁姑問題は昔も...
1位その他離婚理由弁護士監修2019.07.25姑が嫌いすぎて我慢できない!嫁姑問題を理由に離婚できるのか夫はうまくやっているけれど、姑との折り合いが悪い… 嫁姑問題は昔も... -
 2位その他離婚理由弁護士監修2020.09.11マタニティーブルーとは|妊娠中に離婚を考えてしまう理由と克服方法「マタニティーブルー」という言葉をご存じでしょうか。妊娠中や出産直後は子供が生ま...
2位その他離婚理由弁護士監修2020.09.11マタニティーブルーとは|妊娠中に離婚を考えてしまう理由と克服方法「マタニティーブルー」という言葉をご存じでしょうか。妊娠中や出産直後は子供が生ま... -
 3位その他離婚理由弁護士監修2021.05.27立会い出産は離婚率が高い?メリット・デメリットと離婚を回避するコツ立会い出産は、子供が生まれる感動や苦労を夫婦で共有することができます。しかし、立...
3位その他離婚理由弁護士監修2021.05.27立会い出産は離婚率が高い?メリット・デメリットと離婚を回避するコツ立会い出産は、子供が生まれる感動や苦労を夫婦で共有することができます。しかし、立... -
 4位その他離婚理由弁護士監修2020.12.25帰宅恐怖症(帰宅拒否症)とは|改善法と離婚したいと言われたときの対処法「夫がまっすぐ家に帰ってこない」とお悩みの方もいるでしょう。特別仕事が忙しいわけ...
4位その他離婚理由弁護士監修2020.12.25帰宅恐怖症(帰宅拒否症)とは|改善法と離婚したいと言われたときの対処法「夫がまっすぐ家に帰ってこない」とお悩みの方もいるでしょう。特別仕事が忙しいわけ... -
 5位その他離婚理由弁護士監修2021.08.16旦那が逮捕されたので離婚したい|離婚手順と解決に向けてすべきこと何らかの理由で旦那が逮捕されたら、どうしたら良いのかわからず、パニックになってし...
5位その他離婚理由弁護士監修2021.08.16旦那が逮捕されたので離婚したい|離婚手順と解決に向けてすべきこと何らかの理由で旦那が逮捕されたら、どうしたら良いのかわからず、パニックになってし...
新着離婚コラム
-
 その他離婚理由2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま...
その他離婚理由2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま... -
 その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み...
その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み... -
 親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の...
親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の... -
 DV・モラハラ2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?...
DV・モラハラ2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?... -
 裁判・調停2025.05.02離婚の調停調書の効力とは?公正証書との違いや確認すべきポイント離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は...
裁判・調停2025.05.02離婚の調停調書の効力とは?公正証書との違いや確認すべきポイント離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は...
離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!
離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!
離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。
離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!
離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。












