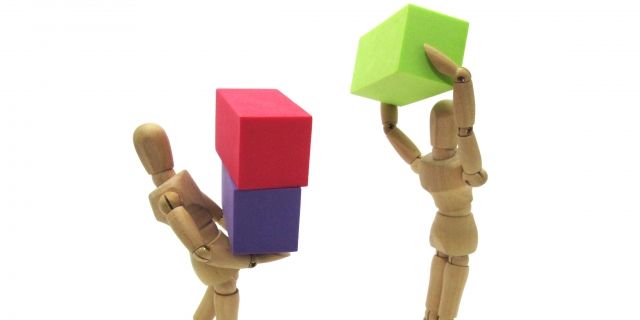離婚後300日問題とは。愛する我が子を無戸籍にさせないために。

離婚後300日問題とは、離婚後300日以内に生まれた子は別れた夫の子と推定するという民法のルールによって、さまざまな支障を引き起こしていることをいいます。
別れた夫の子供でないことが確実で、かつ、我が子を別れた夫の子供として戸籍登録したくないために、やむを得ず子供を無戸籍にしてしまうケースもあるのです。
この記事では、離婚後300日問題とは何か、それに伴いどのようなトラブルが起きているのかを解説します。
- 目次
離婚後300日問題の根源は「民法772条の嫡出推定」
「離婚後300日問題」ルールは、民法772条「嫡出(ちゃくしゅつ)の推定」に記載されています。その全文は次のとおりです。
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
嫡出とは、子供が結婚関係にある夫婦から生まれることです。
覆すことが難航する「父親推定」
- 民法772条を噛み砕いた文章にするとこうなります。
-
- 結婚が成立している期間に妻が妊娠したら、例えその妻が別の男性の子供を宿していたとしても、夫の子供であると推定する。
- 結婚した日から200日以降に生まれた子供は、夫の子供であると推定する。
- 離婚した日から300日以内に生まれた子供は、別れた夫の子供であると推定する。
①は要するに、民法は、妻が夫以外の男性と性交をして子供をつくることを想定していないのです。
そのため、女性が「この子は元夫の子ではない」と主張しても、その子は元夫の子供であると推定されてしまうのです。
本題は③です。③が「離婚後300日問題」の根源となっています。
民法は不倫の子を想定していない
民法、つまり国や政府はなぜ「離婚した日から300日以内に生まれた子供を、夫の子供であると推定する」必要があるのでしょうか。
まず300日の根拠ですが、性交(受精)から出産までの期間の平均は266日です。また、産科医療では最終生理開始日から280日目を出産予定日にしています。いずれも大体300日です。
つまり民法は、ほぼ破綻状態にある婚姻の最後の1~2カ月の間に、元の夫婦が性交をする可能性を重視しているわけです。
国や政府はなぜ、民法772条を改訂しようとしないのでしょうか。
もし「離婚した日から300日以内に生まれた子供を、夫の子供であると推定する」ことを否定してしまったらなにが起きるのでしょうか。
婚姻の最終日(離婚日の前日)以前に妻が夫以外の男性と性交をして子供をつくる可能性を認めてしまうことになります。
そうなると「①結婚が成立している期間に妻が妊娠したら、例えその妻が別の男性の子供を宿していたとしても、夫の子供であると推定する」というルールまで否定しなければならなくなります。
不貞行為を不法行為ですので、婚姻中に不倫によって子供ができることを想定していません。そのため不倫の子供を保護する思考がないのです。
嫡出推定の合理性
法務省は「離婚後300日問題」ルール(嫡出推定)の必要性について、「父子関係を早期に安定させるため」としています。
また、嫡出推定のルールがなければ、「誰からでも、いつまでも法律上の父子関係を否定することができてしまう」とも述べています。
つまり嫡出推定にも一定の合理性があるのです。 ただ個別のケースをみていくと、やはり問題が残るのです。
参考:法務省「無戸籍でお困りの方へ よくあるご質問(https://www.moj.go.jp/MINJI/faq.html)」※1
民法は「妻」に厳しすぎるのではないか
以上は法律の話なのですが、よくあるケースについて見てみます。
【暴力夫と別居しているときに助けてくれた男性の子供を離婚後300日以内に産むケース】
女性Aは、夫Bの暴力に悩み別居をしました。AとBは別居のかなり前から性交はなく、別居後も性交していません。AはBに何度も離婚を求めましたが、Bはなかなか応じませんでした。
そのうち女性Aに新しい恋人Cができ、AとCは自然の成り行きで性交をしました。暴力夫Bがその後、離婚を受諾したため離婚が成立しました。女性Aと新恋人Cはその直後に結婚しました。
そして離婚から200日後に子供Dが生まれました。
「暴力夫の子とする」か「無戸籍」かの残酷の選択
女性Aは婚姻中に夫ではない男性Cと性交しているので、法律的には不倫したことになります。
しかし、当時の状況を踏まえるとどうでしょうか。
暴力夫に悩まされている妻が、婚姻中に次の結婚生活に向けて準備をすることは問題ないはずです。そのとき性交や妊娠が生じたら「ダメ」とするのは妻に厳しすぎるのではないでしょうか。
しかし上記のケースでは、民法は「その子供Dの父親は元夫Bである」と推定します。
もし女性Aが市役所に「この子Dは今の夫Cの子供である」といった内容の出生届を出しても、市役所は受理しません。
子Dの戸籍をつくるには、女性Aは「この子Dの父親は元夫Bである」と市役所に届け出るしかありません。
女性Aが「この子Dの父親は元夫Bである」と届け出ることを拒否すれば、子Dは無戸籍になり、義務教育を受けることも選挙権を得ることもできません。これはかなり残酷な選択です。
元夫ではなく新しい夫の子と届け出るためには妻の負担が大きすぎる
元夫ではなく、新しい夫の子供であると市役所に届け出て、子供の戸籍をつくる方法もあります。
それは、元夫に「家庭裁判所に嫡出否認の訴え(その子は自分の子供ではないという訴え)を申し立ててもらう方法」です。つまり、元夫が家庭裁判所に出向き、「元妻が最近子供を産んだが、その子は自分の子ではない」と申し出るということです。
妻は元夫にそれを依頼しなければならず、負担が大きくなります。
先述のケースで考えると、元夫の暴力から逃げるために別居して離婚までしたのに、女性のほうからわざわざ会いに行き、元夫に「家庭裁判所に行って面倒な手続きをしてほしい」と依頼しなければなりません。そのほかにも方法はありますが、どれも難しい法手続きが必要になります。
「不倫の代償」とはいえ、その負担は妻に大きすぎる印象があります。
国も無戸籍問題改善に動き始めているが遅い
朝日新聞は2017年12月6日の社説のなかで
「離婚後300日問題」ルール(嫡出推定)による無戸籍問題について、国会や政府は本腰を入れて取り組むべきだ
と、民法改正に動かない政治家たちを批判しています。
確かに改善に向けた取り組みもみられますが、その動きはとても遅いといわざるをえないようです。
現在60代になる女性が「嫡出推定の規定は憲法に違反する」として、国に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
この女性は過去に夫の暴力から逃げるために別居をしました。その後、前夫との離婚成立前に女性は別の男性との間に娘を産みました。
役所に前夫とは別の男性の子供として出生届を出しましたが、嫡出推定によって受理されませんでした。そのため女性の娘は無戸籍になり、さらにその娘の子(女性の孫)も無戸籍になりました。
女性の娘はパスポートをつくれず、孫は小学校入学前の健康診断の連絡が届きませんでした。
裁判所は女性の請求は退けましたが、妻に嫡出推定を否定する権利を認めることも選択肢のひとつで、国会は制度を整備すべきだ、としました。
この裁判官は、妻にも「この子の父親は元夫ではなく、新しい夫の子供である」と申立てる権利を与えてもいいはずだ、と考えているわけです。
これは前進ではありますが、裁判官は民法を改正できません。民法を含むすべての法律は国会議員たちでつくる国会でしか修正できないのです。
参照:朝日新聞 社説 「無戸籍問題 解消に向け、動き出せ(https://www.asahi.com/articles/DA3S13260826.html)」 ※2
まとめ
無戸籍の子供が増えるのは由々しき問題です。
DVやモラハラなどから非難し、離婚を考えているが離婚できないという方も少なくありません。しかし、必要な手続きを踏まずに成り行きで行動してしまうことはトラブルを招く恐れがあります。
このような場合は弁護士と一緒に適切に離婚手続きを進めていくことをおすすめします。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
※1 法務省「無戸籍でお困りの方へ よくあるご質問」
※2 朝日新聞 社説 「無戸籍問題 解消に向け、動き出せ」
関連記事≫≫
夫(妻)の暴力から逃れたい! DVの証拠集めとうまく逃げる方法とは。
離婚に強い弁護士の選び方って?弁護士選びで失敗しないポイント。
都道府県から弁護士を検索する
離婚コラム検索
離婚の親権・養育費のよく読まれているコラム
-
 1位親権・養育費弁護士監修2020.03.30養育費を払わない方法|払えない・払いたくないなら知るべき7つのこと子供を持つ夫婦が離婚すると、親権を持たない親は親権者に対して養育費を支払う必要が...
1位親権・養育費弁護士監修2020.03.30養育費を払わない方法|払えない・払いたくないなら知るべき7つのこと子供を持つ夫婦が離婚すると、親権を持たない親は親権者に対して養育費を支払う必要が... -
 2位親権・養育費弁護士監修2019.02.28離婚後に扶養控除はどうなる?子供がいる場合の扶養手続き専業主婦やパートタイマーなどをしていて子供と夫の扶養に入っている人も多いでしょう...
2位親権・養育費弁護士監修2019.02.28離婚後に扶養控除はどうなる?子供がいる場合の扶養手続き専業主婦やパートタイマーなどをしていて子供と夫の扶養に入っている人も多いでしょう... -
 3位親権・養育費弁護士監修2019.07.29子連れ再婚|子供を連れて幸せな再婚をするために知るべき7つのこと1人で子供を育てていると、心細くなったり、誰かに支えてもらいたいと思ったりするこ...
3位親権・養育費弁護士監修2019.07.29子連れ再婚|子供を連れて幸せな再婚をするために知るべき7つのこと1人で子供を育てていると、心細くなったり、誰かに支えてもらいたいと思ったりするこ... -
 4位親権・養育費弁護士監修2019.01.15離婚後に子供を元配偶者と面会させたくない!拒否はできる?離婚して子供の親権を獲得した人が、元配偶者から「子供と会いたい」と言われたとき、...
4位親権・養育費弁護士監修2019.01.15離婚後に子供を元配偶者と面会させたくない!拒否はできる?離婚して子供の親権を獲得した人が、元配偶者から「子供と会いたい」と言われたとき、... -
 5位親権・養育費弁護士監修2019.01.10親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?子供を持つ夫婦が離婚する際に問題になるのは親権者指定です。親権獲得は母親のほうが...
5位親権・養育費弁護士監修2019.01.10親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?子供を持つ夫婦が離婚する際に問題になるのは親権者指定です。親権獲得は母親のほうが...
新着離婚コラム
-
 親権・養育費2025.07.07子の引渡しを成功させて親権を獲得する方法と知っておくべき5つの事「配偶者が突然子供を連れて家を出ていった」 「連れ去られた子供を取り戻したい」こ...
親権・養育費2025.07.07子の引渡しを成功させて親権を獲得する方法と知っておくべき5つの事「配偶者が突然子供を連れて家を出ていった」 「連れ去られた子供を取り戻したい」こ... -
 その他離婚理由弁護士監修2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま...
その他離婚理由弁護士監修2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま... -
 その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み...
その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み... -
 親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の...
親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の... -
 DV・モラハラ弁護士監修2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?...
DV・モラハラ弁護士監修2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?...
離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!
離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!
離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。
離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!
離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。