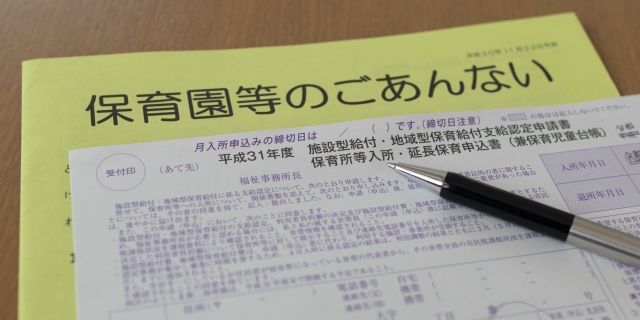育児休業給付金とは|育休中に離婚を考えたら知っておくべきこと

出産直後や育休中といえば、「子供が生まれて幸せに違いない」と思われるかもしれませんが、女性が離婚を考えることの多い時期でもあります。
会社で働いている人が育児休業を取る際、条件を満たせば育児休業給付金がもらえます。
離婚時には財産分与や養育費などを決めることになりますが、育児休業給付金はどう扱われるのでしょうか。
この記事では、離婚時の育児休業給付金の扱われ方や育休中に離婚する際に注意すべきことを解説します。
- 目次
育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、条件を満たす人が育児休業中(以下、育休中)に申請することで受け取れる給付金です。
育休を取得した従業員は出勤したり、仕事をしたりすることができません。会社としても育休中の従業員に通常の給料を支払うわけにもいきません。
育児休業給付金とは、育休中(給料が支給されていない期間)、収入を補填する目的で支給される手当です。
令和4年10月1日、育児・介護休業法が改正されました。
これにより、1歳未満の子供に対する育児休業について、原則2回まで育児休業を分割して取得でき、育児休業給付金も2回まで分割して受給できるようになりました。
また、男性の育休取得促進を目的とした産後パパ育休(出生時育児休業)が新設されました。
なお、育児休業と育児休暇には以下のような違いがあります。
- 育児休業:育児・介護休業法に基づき、取得できる休業制度
- 育児休暇:育児のために取得する休暇。法律で定められたものではない
本記事では「育児休業=育休」として説明します。
【出生時育児休業給付金が新設】
前述のとおり、育児・介護休業法の改正により、男性の育休取得促進を目的とした産後パパ育休(出生時育児休業)が新設されました。
出生時育児休業(産後パパ育休)を取得し、一定条件を満たした場合、出生時育児休業給付金を受給できます 出生時育児給付金の受給要件は以下です。
- 子供の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間(28日)以内で産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者であること(2回まで分割取得可)
- 休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること
- 休業期間中の就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)であること
なお、休業期間中の就業日数の「最大10日」とは、28日間の休業を取得した場合の日数になります。休業期間が28日より短い場合は日数に応じて短縮されます。
また、有期雇用契約者の場合、上記に加えて下記についても満たす必要があります。
- 子供の出生日(出産予定日までに子供が生まれた場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了することが明らかでないこと
出生時育児給付金の申請は、養育する子供の出生日から8週間を経過する日の翌日から提出可能です。申請期限は当該日から2か月を経過する日の属する月の末日になります。
なお、支給額は育児休業給付金と同じ計算式で算出されます。出生時育児給付金の離婚時の扱われ方については弁護士にご相談ください。
参考:育児休業給付金の内容と支給申請手続き (https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf)※1
育児休業給付金の受給条件
育児休業給付金は雇用保険から支払われます。したがって、育児休業給付金を受け取るためには雇用保険に加入している必要があります。そのほかの受給条件は以下となります。
- 1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得していること
- 育休前の2年間で賃金支払基礎日数が11日以上または就業した時間数が80時間以上ある完全月が12か月以上あること
- 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること
なお、一支給単位とは育児休業を開始した日から数えて1ヶ月ごとの期間を指します。
【有期雇用契約の場合】
契約社員やパートなど、有期雇用契約で働いている方は上記の受給条件に加えて以下の条件も満たす必要があります。
- 養育する子が1歳6か月に達する日までの間に労働契約期間が満了することが明らかでないこと
なお、ここで言う労働契約期間について、労働契約が更新される場合は更新後の期間になります。
また、保育所などで保育をしてもらえない場合、子供が1歳6ヶ月に達する日の後も育児休業を取得する場合は2歳に達する日までの期間とします。
有期雇用契約の場合の育児休業給付金の受給条件について、法改正前は「引き続き雇用された期間が1年以上」という条件がありましたが、改正後はなくなりました。
【育児休業給付金を受給できないケース】
育児休業給付金は受給資格を満たす必要があります。つまり、以下のような場合は育児休業給付金を受給できません。
- 雇用保険に加入していない場合
- 育児休業を取得しない場合
- 一人の子供に対して3回以上にわけて育休を取得した場合の3回目以降の育児休業の場合
- 育児休業を取得後、復職予定がない場合 育休中に退職した場合
- 育休中に育児休業前の給料の80%以上の金額が支給されている場合
育児休業給付金の受給期間

育児休業給付金の受給期間は、分娩の翌日から8週間経過(産後休業期間)後から養育している子供が1歳になった日の前日までが原則です。子供が1歳になる前に復職する場合は復帰日前日までとなります。
なお、一定要件を満たす場合は最大で子供が1歳6ヶ月または2歳となった日の前日まで受給可能な場合もあります。これについては「育児休業給付金の受給期間は延長できるのか」にて後述します。
育児休業給付金の申請方法
出生時育児休業給付金・育児休業給付金ともに雇用主(勤務先の会社)が申請を行うのが一般的です。しかし、状況によっては自分で申請を行うケースもあります。
【育児休業給付金の申請の流れ】
育児休業給付金は、必要な書類を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出することで申請します。
【育児休業給付金の申請に必要な書類】
- 育児休業給付金の申請の際に必要な書類は下記です。
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付金支給申請書 ※初回のみ
- 育児休業給付受給資格確認票 賃金台帳や出勤簿、タイムカードなど ※雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記載内容を確認できる書類
- 母子健康手帳の出生届の写しや住民記載事項証明など ※育休中であることを確認できる書類
- 育児休業給付金受取口座の通帳の写し
なお、育児休業給付金支給申請書、育児休業給付受給資格確認票には払渡希望金融機関指定届がついています。
以前、この口座で雇用保険関係の給付を受けていたという場合はそのまま使用することも可能です。
また、マイナポータルに公金受取口座を登録しており、ハローワークにマイナンバーを届け出ている場合はその口座を利用することも可能です。
育児休業給付金の支給額
育児休業給付金は受給期間中に金額が変わります。
- 育児休業開始から180日まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
- 育休開始から181日以降、育児休業最終日まで:休業開始時賃金日額(育児休業開始前6か月間の賃金を180で割った金額)×支給日数×50%
休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6か月間の賃金総額を180で割った金額です。
育休開始前の2年間に完全な賃金月が6ヶ月に満たない場合、賃金の支払いの基礎となる時間数が80時間以上である賃金付き6ヶ月の間に支払われた賃金の総額を180で割った金額になります。
育児休業給付金支給期間中に給与が支払われる際、支払われた給与金額が休業開始時賃金月額×13%を超えて80%未満である場合には育児休業給付金の支給額が減額されます。
また、休業開始時賃金月額の80%以上となる場合、育児休業給付金は支給されません。
【育児休業給付金の支給額には上限がある】
育児休業給付金の支給額には上限があります。支給日数が30日の場合は以下が上限となります。
- 育児休業開始から180日まで(休業開始時賃金日額×支給日数の67%が支給される場合):30万5,319円
- 181日から育児休業最終日まで(休業開始時賃金日額×支給日数の50%が支給される場合):22万7,850円
【育児休業給付金の具体例】
ここからは月給23万円の人が出産後一年間会社を休んだ場合の育児休業給付金の具体例を紹介します。
- 育児休業開始日から180日 23万円×67%=15万4,100円/月
- 181日から育児休業終了日まで 23万円×50%=11万5,000円/月
育児休業給付金を受給する際の注意点
育児休業給付金受給する際にはいくつか注意点があります。
【育児休業給付金の申請には期限がある】
育児休業給付金の申請期限は以下となります。
- 受給資格確認手続きのみを行う場合:初回の支給申請日まで
- 初回の支給申請も併せて行う場合:育休開始日から4か月が経過する日の属する月の末日まで
【育児休業給付金は産後休業期間が終わってから支給される】
育児休業給付金の受給期間は、分娩の翌日から8週間経過(産後休業期間)後から子供が満1歳の誕生日を迎える前日、あるいは父親または母親が職場復帰するまでで、最大10か月間となります。
【育児休業給付金を継続して受け取るためには】
継続して育児休業給付金を受け取るためには、初回の申請手続き後、2か月ごとに申請書を提出する必要があります。
なお、育児休業給付金は、最初の申請で育休開始から2ヶ月分の休業状況を審査し、1回目の振込が行われます。2回目以降、同様の審査が2ヶ月ごとに行われ、その後振り込まれます。
申請後、休業状況の審査に約2週間程度かかります。また、「育児休業給付金決定通知書」が送付後、入金されるまで約1週間かかります。
【社会保険料の免除を受けるには申請が必要】
育休中の健康保険や厚生年金といった社会保険料は、事業主と被保険者ともに免除されます。
ただし、育休中に社会保険料の免除を受けるためには、事業主が日本年金機構に「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。
育児休業を取得する際は必ず会社や担当部署に確認するようにしましょう。
【会社から給与が支給された場合は雇用保険料を納める】
育休中に会社から給与が支給された場合は雇用保険料を納める必要があります。
育児休業給付金の受給期間は延長できるのか
原則として育児休業給付金の受給期間は延長できません。
ただし、子供の1歳の誕生日後に育休を取得する際、例外的に1歳6か月に達する日の前日まで育児休業給付金の受給期間を延長できるケースがあります。
また、子供が1歳6ヶ月後に達する日後に育休を取得する際、子供の2歳の誕生日の前日まで育児給付金の受給期間を延長ができるケースがあります。
ではどのようなケースで延長が認められるのでしょうか。
【①保育所などに申し込みを行ったが保育所の理由で預けられない場合】
保育所(認可外保育施設を除く)などに申し込みを行ったにも関わらず、保育所側の理由で子供を預けることができず、職場復帰ができない場合は育児休業給付金の受給期間の延長が認められています。
このとき、以下の3つの要件をすべて満たすことが前提となります。
- 入所申込みを子供の1歳の誕生日の前日(または1歳6ヶ月に達する日)以前に行っていること
- 入所希望日が子供の1歳の誕生日(または1歳6ヶ月に達する日の翌日)の属する月かつ1歳の誕生日の翌日以降でないこと
- 1歳の誕生日(または1歳6ヶ月に達する日の翌日)以後の期間において当面保育の実施が行われないこと
【②養育者が死亡あるいは疾病などで職場復帰困難な場合】
養育者が死亡あるいはケガや病気で養育ができない場合は職場復帰が難しくなります。このようなケースも育児休業給付金の受給期間の延長が認められます。
【③養育者が妊娠中や産後間もない場合】
養育者が育休中に新たな妊娠をして出産間近あるいは産後直後という場合、子供の養育ができず、職場復帰が難しいことがあります。このような場合も育児休業給付金の受給期間の延長が認められます。
【④離婚によって養育者と子供が同居できなくなった場合】
離婚などの理由で養育者と子供が別々に暮らさざるを得なくなったという場合も職場復帰が難しいため育児休業給付金の受給期間の延長が認められます。
【パパ・ママ育休プラス】
パパ・ママ育休プラスとは母親と父親がともに育児休暇を取得する際、1年間の育休期間を2か月(子供が1歳2か月になるまで)延長できる制度です。
パパ・ママ育休プラスを利用するためには以下の要件を満たす必要があります。
- 子供が1歳に達するまでの間に配偶者が育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が子供の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業初日以降であること
なお、育休取得期間自体は延長前と同じく最大1年間です。子供が1歳2か月になるまでの間、夫婦がそれぞれで与えられた1年間の育児休業を振り分けることができるという制度です。
参考:厚生労働省「パパ・ママ育休プラス(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/0019/papamama.pdf)」※2
育児休業給付金の受給期間を延長するための手続き
育児休業給付金の受給期間を延長する際は育児休業給付金支給申請書に必要事項を記入し、延長事由に該当していることを確認できる書類を添付して提出します。
【育児休業給付金の受給期間の延長手続きに必要な書類】
育児休業給付金の受給期間の延長は、子供が1歳の誕生日後の延長、1歳6ヶ月に達する日後、それぞれについて手続きが必要になります。
育児休業給付金受給期間の延長手続きには以下の書類が必要です。
- 育児休業給付金支給申請書
- 受給期間延長事由に該当していることを確認できる書類
育児休業給付金の受給期間延長事由に該当していることを確認できる書類には以下のようなものがあります。
- ①の場合:市町村が発行した保育所の入所保留の通知書など
- ②の場合:世帯全員について記載された住民票の写しおよび母子健康手帳や養育者の病状についての医師の診断書
- ③の場合:産前産後に係る母子健康手帳
- ④の場合:世帯全員について記載された住民票の写しおよび母子健康手帳
なお、①~④は「育児休業給付金の受給期間は延長できるのか」の項に記載した延長理由のいずれかになります。
提出先は受給申請時と同様に事業所の所在地を管轄するハローワークになります。
育休中に離婚したいと思ったら
育休中に離婚した場合、受給している育児休業給付金はどうなるのでしょうか。
【育休中に離婚した場合は育休や給付金の延長はできない】
育休中に離婚した場合、育休や育児休業給付金の受給期間を延長したいと思う方もいるかもしれません。
育休中に離婚する場合、「主に母親が子供を養育し、育休期間中に離婚。離婚後の子供の親権者は母親」というケースが一般的です。
しかし、このような場合、育児休業給付金の受給期間を延長することは認められません。
離婚に伴う育児休業給付金の受給期間の延長は、「養育者と子供が別々に暮らさざるを得なくなった場合」に限り、認められるものです。
例えば、「主に子供を養育していた母親と離婚、父親が子供を引き取ったが育てる人がいない」というケースであれば、延長できる可能性もありますが、その他の条件も含め、現実的には延長が認められるのは非常に稀と言えます。
【育児休業給付金を受給中の婚姻費用や養育費はどう計算されるのか】
離婚を検討する際、別居してから離婚するかどうかを考えるケースも多いです。
夫婦には婚姻費用(結婚生活に必要な生活費)分担義務があるため、別居中であっても収入の多い側に婚姻費用を請求することができます。
また、育休中ということは未成年の子供がいるわけですから、離婚後に親権を持たない親(非監護親)には養育費分担義務があります。そのため、非監護親に対して養育費を請求することができます。
産休中や育休中に会社から給与が支給されている場合は源泉徴収票や給与明細によって基礎収入を計算し、婚姻費用や養育費を算出することになります。
では給与が支給されず、育児休業給付金が支給されている場合はどうなるのでしょうか。この場合、以下の2つのケースが考えられます。
- 育休中と育休後にわけて算出する
- 育休中の収入で計算し、育休終了後に金額の変更を申し出る
ただし、婚姻費用や養育費は家庭の状況や事情を考慮して総合的に判断されるものです。育児休業給付金受給中の婚姻費用や養育費の計算については弁護士に相談することをおすすめします。
【育児休業給付金は財産分与の対象になるのか】
離婚する際、婚姻中の共有財産を夫婦で公平に分けます。これを財産分与と言います。では、育休中に支給された育児休業給付金は財産分与の対象になるのでしょうか。
育児休業給付金は給料ではなく休業手当のようなものです。そのため育児休業給付金は財産分与の対象となりません。
【職場復帰してから離婚することも検討しよう】
主に子供の養育に携わっているのが母親の場合、離婚後の親権は母親が持つ可能性が高いでしょう。
しかし、育児休業給付金は「離婚してシングルマザーになった」という理由だけで延長を認めてもらうことは難しいのが現実です。
育児休暇中に離婚し、1歳前後の子供を育てながら仕事に復帰するのは大変です。
DV被害に遭っているなど、やむを得ない事情を除き、まずは職場復帰して生活を安定させ、それから離婚するかどうかを考えるという選択肢も視野に入れておきましょう。
まとめ
育児休業給付金の申請方法や育休中に離婚する際の育児休業給付金の扱われ方について説明しました。
育休中に離婚を考える人は多いですが、まずは職場復帰して生活を安定させることも視野に入れましょう。どうしても離婚をしたいというなら、デメリットも踏まえて慎重に検討する必要があります。
離婚問題に強い弁護士なら、離婚の際の育児休業給付金の考え方や相談者の状況に合わせた解決策をアドバイスしてくれます。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。育休中に離婚を考えたら一人で悩まず、弁護士に相談することをおすすめします。
※1 厚生労働省「育児休業給付金の内容と支給申請手続き」
※2 厚生労働省「パパ・ママ育休プラス」
関連記事≫≫
育児に非協力的な夫と離婚できる?ワンオペ育児で離婚にいたる原因と対処法。
子供の親権を勝ち取るために離婚前にすべきこと|親権の相談は離婚弁護士へ
母子家庭向けの手当や制度って?シングルマザーが安定して暮らす方法
産後クライシス|離婚を回避して夫婦仲を改善する方法とは
離婚の養育費の相場|できるだけ多くもらう方法とは
都道府県から弁護士を検索する
離婚コラム検索
離婚の基礎知識のよく読まれているコラム
-
 1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ...
1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ... -
 2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです...
2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです... -
 3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と...
3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と... -
 4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚...
4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚... -
 5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...
5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...
新着離婚コラム
-
 親権・養育費2025.07.07子の引渡しを成功させて親権を獲得する方法と知っておくべき5つの事「配偶者が突然子供を連れて家を出ていった」 「連れ去られた子供を取り戻したい」こ...
親権・養育費2025.07.07子の引渡しを成功させて親権を獲得する方法と知っておくべき5つの事「配偶者が突然子供を連れて家を出ていった」 「連れ去られた子供を取り戻したい」こ... -
 その他離婚理由弁護士監修2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま...
その他離婚理由弁護士監修2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま... -
 その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み...
その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み... -
 親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の...
親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の... -
 DV・モラハラ弁護士監修2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?...
DV・モラハラ弁護士監修2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?...
離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!
離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!
離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。
離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!
離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。